アニクリvol.6.1「夜は短し歩けよ乙女+四畳半神話大系特集(仮)」の発刊について:2017年文フリ #bunfree
1、検討・寄稿募集作品:
(1)夜は短し歩けよ乙女
(2)四畳半神話大系
2、寄稿募集要項
(1)募集原稿:上記2作にかかる評論、批評、二次創作等々
(2)装丁・発刊時期:
モノクロ小冊子、A5、28頁程度で企画しています。
発刊時期は、2017年春の第24回東京文フリ(5月)を想定しています。
(3)募集原稿様式
a. 文字数:
①論評・批評 : 3000字程度から15000字程度まで。
②作品紹介・コラム:500字程度から2000字程度まで。
b. 形式
.txt または .doc
c. 締め切り
第一稿:2017/5/1
(※ 個別に連絡いただけましたら延長することは可能です)
(※ その後、何度か原稿の校正上のやり取りをさせていただけましたら幸いです。)
最終稿:2017/5/5
d. 送り先
anime_critique@yahoo.co.jp
※ 参加可能性がありましたら、あらかじめご連絡いただけましたら幸いです。その際、書きたい作品、テーマ、内容についてお知らせくださると、なお助かります。
※ 原稿内容について、編集とのやりとりが発生することにつき、ご了承ください。
(4)進呈
寄稿いただいた方には、新刊本誌を進呈(※ 進呈冊数は2を予定)させていただきます。
3、企画趣旨代わりの小噺がてら
思い出せば随分昔のことになるのでしょうが、一つ大して気の利かない小噺を思い出しましたので、一つお耳汚しをば。
※ ちょうど高校2年生の夏になるでしょうか。私は当時東北の仙台で、凡庸極まる夏休み期間を過ごしていたのでした。高校からはじめた弦楽器が滅法に面白く思えた私は、起きてから寝るまでの間、空いた時間は殆ど楽器にしか触らないような生活を送っていたのですが、その甲斐あって、(今考えれば)随分面倒見の良かった先生に、随分なご厄介をかけるようになっていました。
今となっては動機が何だったのかは最早思い出せません。あえて思い返そうとするならば、私を見兼ねた先生が仰ったのだと、「どこか興味のある大学のオープンキャンパスにでも行ってきなさい」と、その先生はただの一学生を広い学内から探し出して、わざわざ最上階の(音が響きづらい)倉庫兼部室にまで言伝に来てくれたのだと推し計れます(もしそうでなければわざわざは遠出しなかったくらいには不精かつ音楽に没頭していたために、そうとしか思えないのです)。
当時の先生を美化するべきなのかどうかは、いまになっては判りかねます。ギリギリとはいえ既に21世紀でしたから、某省的な圧力があったのかもしれませんし、そもそも「オープンキャンパス」というような軽薄な響きのイベントごとに当時の私が勇んで参加したかすら定かではありません。その証拠とはいえませんが事実として、結果としては、私はその年の大学のオープンキャンパスには参加しなかったのでした。
しかし、ならば全く徒労とも言えようことに、私はその年、私の記憶が正しければ(オープンキャンパスが終わった後の何もないはずの)京都大学に足を運んだのでした。それは紛うことなきことなのです。
今となってみれば、オープンキャンパスは大学の主たる宣伝場という印象が強いかもしれませんが、21世紀初頭にあっては、そんな横文字は大して耳慣れた文字列ではなかったはずです。ともかく、そんな行事が催されているという話を耳にし、Windows98搭載PCで検索をしていた記憶が蘇ります。ただし、調べた結果としてはオープンキャンパス自体は残念ながら開催日を終えていたのでした。
では諦めるかといえばそうではなく、その当時の私は「とりあえず見てくるか」という心算で青春18切符を買いに行ったのです。一つのことを始めると融通が効かずにそのまま事を続けてしまうという悪癖が露出したものと思い出されますが、そこは高校二年生で、明くる朝には仙台から京都に向けての出立のため、家をあとにしたのです。
(あまりにも唐突だったためか、父親が職場から渡されたはずの携帯電話を急ぎ私に渡す羽目になり、それによって仙台で働く父親と首都圏の若い女性との密通の事実を期せずして知ることとなりましたが、未だその事実は露見していないはずでしょう。何事にも正負の側面というものがあるものです。)
そんなこんなでかつては定期便であった「ムーンライトながら」に揺られ京都に到達し、ユースホステルを起点として、大学巡りをすることになりました。同室のよくわからない大学生ら(思い返せばオタクっぽかった。)と話したり、同世代の女学生(なぜあの時期に京都に来ていたのかは全く不明。)を駅まで見送ったりしたような気もしますが、それ自体はまぁ通り一遍の対応で済ませたような気がします。
一つ残念なことに、無鉄砲な私は(オープンキャンパスどころか)偶々お盆休みにかぶる時に大学に向かってしまったようで、図書館にも入れず某寮への侵入も失敗したりと散々な目に会いました。とはいえ、キャンパス内を目的なく徘徊していると、いかにもな大学生や研究者の方々と思しき人々とすれ違うことで勝手な納得感を得ていたような気がします。
さて、思い出した小噺というのはここからです。
その足で、出町柳に向かって歩いていた時、「もし」と声をかけられたのでした。「もし」と声をかけられること自体が(当時ですら)風情があったもので振り返ると、そこには女性が一人、日傘を傾けて立っていたのでした。
雪駄を履いた(なぜ雪駄かといえば、下らないことに私の通う高校に「下駄禁止」の規則があったため。)、見た目はズダ袋にしか見えない帆布リュックを背負う若者にわざわざ話しかけなくてもいいように思うのですが、何故かその人は私を引き止めたのでした。まぁ、東北の片田舎からやって来た洗練されない少年と言うのは、いかにも安全そうに見えるものでしょう。
「綺麗な人だな」というのがこちらから見た第一印象で、立ち止まって話すとどうやら地下鉄の駅に行きたいのに迷っているという話。「私自身も所謂お上りさんなのですが」と言うと、「では一緒に参りましょう」という始末で、「ははぁこれが出来すぎた話というやつか」と思いつつ、彼女を今出川駅までお送りした次第です。
道中ニコニコしながら歩む彼女に「京都の方なのですか?」と頓珍漢な質問(京都人なら迷うわけなかろう。)をする私に、「いえ、普段は大阪の方に住んでおりまして」と彼女は言う。「なるほど、では今日は偶々なわけですね」と返す不甲斐ない私に、「そうですね、今日は親類の関係で来ておりまして。私自身は仙台から来たのです」と彼女は返す。
「なるほど遠い地だから仕方ないですね」と応じつつ、あれ?と思って「私も昨日仙台から来たのです」と付け加えると、先方の顔は見る見る内に綻び、私が通っていた学校(仙台第一)とほぼ同名の学校の名(宮城一女)を、通っていた高校として挙げるのでした。
そこから先は、随分いろいろな話をしたような気がするのですが、あまり覚えていません。覚えているのは、先方が仙台の好きだった菓子屋の話などをするのを、大して上手くない相槌とともにうんうん頷くことしかできなかったと言うことくらいです。
世が世なら、と言うか、私の歳が歳なら、それはとても『夜は短し歩けよ乙女』調だったと言えましょう。実際には「黒髪の乙女」とは些か言いづらいものの、お話しさせていただいたお相手は、白髪混じりでありつつ背筋がピンと張った、初老ではあれ美しい女性ではありました。連絡先すら聞くことはできず(21世紀初頭はそういう風習さえなかった。)、何度もお辞儀をして階段を降りる彼女を、私は今出川で見送ったのでした。
今思い返せば、その女性の向かうべき場所は今出川駅から直通で行ける場所ではなく、やはり私には荷が重かったガイドだったわけですが、スマホもなく、当時は道を尋ねるべき歩行者も少ない(そんな時がかつての御所付近にまだ在ったのです。)まま、ともに見知らぬ京都の地であれこれと考えあぐねて照りつける日差しの中あるき回ったその日の記憶は、ふと意識に浮上してくる記憶の一つとなっているのです。
その後、私は京都の大学と東京の大学(どちらも馬鹿みたいに古い寮があって、とりあえず生活はままなるだろうと言う)のいずれかを選択するにあたり東京の片田舎の方を選んだわけですが、『夜は短し歩けよ乙女』の、恐るるところなしとばかりに進む「黒髪の乙女」を見て、あの時の「袖振り合い」感を僅かながらに思い出したわけです。
私たちは「袖振り合って」どこに行くのか?どこに行くことができるのか?『四畳半神話大系』での遅々とした歩みとは裏腹に、『夜は短し歩けよ乙女』では軽快に「乙女」が進んでいきます。御都合主義と言う揶揄すら届かぬまま、彼女は歩みを進めるのです。酒場から宴会へ、宴会から舞台へ、舞台から四畳半へ。惨めさなど些かも感じないまま、感じさせないまま。イメージからシンボルへ、シンボルからメタファーへ、彼女はくるくる変わる背景の中をずんずんと進みます。
私たちはどこにいるのでしょう?どこに行くことができるのでしょう?そんなことを思いながら、私は「袖振り合う」数々の人たちのことを思うのです。また、そんな数々の人達の袖振り合った数々の人たちのことを、訊きたく思うのです。本作において寄稿を募集すると言うのは、そう言う問いの下にあるように思えてならないのです。
以上
文フリ新刊寄稿募集 アニメクリティークvol.6.6 続・新房昭之ノ西尾維新『続・終物語』 #bunfree

1、検討・寄稿募集作品例:
(1)続・終物語及び関連諸作品
・化物語
・偽物語
・猫物語(黒)
・〈物語〉シリーズ セカンドシーズン
・憑物語
・終物語
・暦物語
・傷物語Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ
(2)新房昭之(総)監督の携わったアニメ作品に関連する評論
(3)他、西尾維新原作作品に関する評論
2、寄稿募集要項
(1)募集原稿:
続・終物語及び関連作品
(2)装丁・発刊時期:
オフセット印刷、A5、32頁程度で企画しています。
発刊時期は、2018年秋の東京文フリ(11月)です。
(3)募集原稿様式
a. 文字数:
①論評・批評 : 1500字程度から15000字程度まで。
②作品紹介・コラム:300字程度から1000字程度まで。
b. 形式
.txt または .doc
c. 締め切り
最終稿:2018/11/23
d. 送り先
anime_critique@yahoo.co.jp
※ 参加可能性がありましたら、あらかじめご連絡いただけましたら幸いです。その際、書きたい作品、テーマ、内容についてお知らせくださると、なお助かります。
※ 原稿内容について、編集とのやりとりが発生することにつき、ご了承ください。
(4)進呈
寄稿いただいた方には、新刊本誌を進呈(※ 進呈冊数は2を予定)させていただきます。
3、企画趣旨
「文字とは、奇瑞を記し、凶兆を知り、天を動かすものである。個人のためにつくられたものではなく、集団に与えられた恩寵だった」(円城塔『文字渦』2018)
「鏡はその裏箔を反映させることはできないが、それなしではそもそもいかなる反映もありえない。鏡の裏箔は下部構造(原-痕跡、差延、代補、再-マーク、反覆可能性)でできており、反映-反省を可能にするものなのだが、それはまた、反映-反省が自己自身へと閉じることを防いでもいる」(ロドルフ・ガシェ 対話「思考の密度」2008年)
本というものには顔があり、裏(奥行き)もある。文字どおり、裏の顔(裏表紙)も、裏の顔の裏(裏表紙裏)もある。文章にも、言葉にも裏の顔(トリック、皮肉 etc.)があり、もしも読まれたならば声にも顔(声音/声色)と裏(裏返り/裏声)がある。解釈が介在する以上、意味が決定不可能な文章というのも存在するし、意味上、映像化不可能な文章というものもまた存在する。
では、解釈を駆動する最小単位、線/文字には顔があるだろうか?線/文字には裏があるだろうか?(文字を鏡写しにしても左右反転にしかみえない。文字が印刷された紙を裏から透かして見ても、左右反転にしかならない。)
上記鏡映反転の現象において知られているように、もしも対象物に奥行きがなければ、裏返す操作と反転(逆転)する操作に見かけ上の違いはない。しかし、線/文字に裏面などないことを認めた上で、線/文字(最小単位、個体、キャラクター etc.)に「裏」を(すなわち奥行きを)与えるならば、その時一体どのようなことが起こるのだろうか?(それは、描かれたキャラクターに”原理的に”書き込まれえない裏面を与えることと、どのくらい似ているだろうか?)
「白黑反轉」(©️傷物語)から「鏡映反転」へ。西尾維新(原作)×新房昭之(監督)『続・終物語』の鑑賞後、編者に浮かんだ疑問は上の通りである。
西尾維新の終わりを与えるはずの物語のそのまた続き、『続・終物語』の映像化は後日談やファンディスクに収まらない。『続・終物語』は、登場人物による自己の解釈を描き、作者による自作品解釈の挫折を描き、そうして、「心残り」からも漏れ出る残りを、虚構の(しかし、真実の別面でもある)像として浮かび上がらせる。ヴェールの奥から身を現さない忍野忍(=反転に耐えられる文字列「忍 野 忍」のその裏面)はその徴(憑)であり、心残りがないはずの戦場ヶ原ひたぎの別の顔はその証(言)である。
西尾維新は、膨大な『物語』の系列、上/下(巻)、白/黒にわたる文字の渦を、自覚的に反覆し、ひたすら反転させてきた。その現在としての『続・終物語』は、自身の本の最小構成要素たる文字を裏返す。別のフィクションの内部に取り込んでしまう荒技を映像化するもの、端点を繰り延べるものとして『続・終物語』はある(はずである)。
文字の映像化の限界とともに、文字に「裏」を与えるもの、端点(終わり/はじまり)を裏返すもの、(永井均/森見登美彦の比喩を借りるならば)表返された世界-袋。『続・終物語』をそういうものとして読み解いたら、どのような展望が開けるだろうか。
vol.6.6の発刊趣旨は以上である。
以上
------以下は、vol.6.0の情報
「表紙


目次
I Outline
1.1 ねりま @AmberFeb
いまを途中から生きる
II Technology→Narratology
2.1 Dieske @diecoo1025
アニメ『化物語』における「キネティック・タイポグラフィ」再考ー「おもし蟹」の表象に見る「ひたぎクラブ」の主題
2.2 tacker10 @tackerx
失われた接点(キス)を求めて ー「西尾維新×新房昭之×シャフト」論
2.3 橡の花 @totinohana
文脈的「モンタージュ」
III Metaphor→Metonymy
3.1 みら @paranoid3333333
鉄血にして/熱血にして/冷血の吸血鬼 ー分断され接続する『傷物語』について
3.2 あんすこむたん @deyidan
ビジュルアル×トリック ークビキリサイクルと終物語
3.3 ぽんてぃーぬ
映画『傷物語』の力学 ー青年期の終わりと「これからの日本」
3.4 今村広樹 a.k.a yono @iyono
なぜメフィスト賞作家で西尾維新作品の映像化が多いのかについて少し考えてみた
本文







(ページサンプルは後日挿入)
------------------------------------------以下、発刊趣旨など
1、検討・寄稿募集作品例:
(1)「物語」シリーズ
・化物語
・偽物語
・猫物語(黒)
・〈物語〉シリーズ セカンドシーズン
・憑物語
・終物語
・暦物語
・傷物語Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ
(2)「戯言」シリーズ
・クビキリサイクル 青色サヴァンと戯言遣い
(3)新房昭之(総)監督の携わったアニメ作品に関連する評論
・コゼットの肖像
・ぱにぽに
・ef
・ひだまり
・まどマギ
・打ち上げ花火
など
(3)他、西尾維新原作作品に関する評論
2、寄稿募集要項
(1)募集原稿:
新房昭之×西尾維新をテーマに寄稿募集を行います。折しも、三部作となった『傷物語』がこの2017年1月の公開をもって完結し、シャフト×新房も10年を過ぎた現在、新房(総)監督による西尾維新作品のアニメ化についての総括を行うのが適切であると考え、今回の企画に臨んだ次第です。
さて、新房監督といえば、かつて『幽☆遊☆白書』で激しいアクションを指示するコンテ・演出から、トメの多用やカット数をふんだんに利用した近時のシャフト諸作品まで、幅広い作品を手がけて監督です。例えば、トメの多用については監督本人曰く、現場の制作環境の過密さを緩和するための手法であったともされており、純粋に表現面からの要請とは異なる面から意図的に映像作りをしているとの姿勢も見え、『アニクリ vol.5.0「アニメにおける資本」号』との連続性も意識して同人誌作りができるものと考えています。
もちろん、新房監督も株主兼制作パートナーとして参加するeggfirmの活動なども含め、アニメをめぐる環境に踏み込んだ検討も募集しています。
また、西尾維新といえば、文字媒体の特質を遺憾なく発揮した文体・語彙選択で知られているわけですが、そのような作品をアニメ化するに際しての巧拙や功罪については、各人の思うところがあるのではないかと思料します。とりわけ、西尾作品についてはプリプロ段階での緻密な検討が要求されると目されることから、この点についての言及を有する批評については特に力を入れてご寄稿いただけましたら幸いです。
※ もちろん、作品評論の常として、どこまでが新房昭之・西尾維新によるものかという線引き問題は生じる(例えば、新房は原作者の参加(クレジットにせよ脚本会議にせよ)を積極的に促す監督として知られるが、原作者との距離はどうか? 例えば、尾石、大沼、宮本、川畑等々との「分業」の度合いはどうか?)ものの、この点を含めた議論喚起をなすべく、この度の寄稿募集を行った次第です。
※気になる読者は、おはぎ(@ohagi2334)さんのクレジットリストに詳しいので、参照してください。
(2)装丁・発刊時期:
オフセット印刷、A5、100頁程度で企画しています。
発刊時期は、2017年春の第24回東京文フリ(5月)を想定しています。
(3)募集原稿様式
a. 文字数:
①論評・批評 : 3000字程度から15000字程度まで。
②作品紹介・コラム:500字程度から2000字程度まで。
b. 形式
.txt または .doc
c. 締め切り
第一稿:2017/3/25
(※ 個別に連絡いただけましたら延長することは可能です)
(※ その後、何度か原稿の校正上のやり取りをさせていただけましたら幸いです。)
最終稿:2017/4/15
d. 送り先
anime_critique@yahoo.co.jp
※ 参加可能性がありましたら、あらかじめご連絡いただけましたら幸いです。その際、書きたい作品、テーマ、内容についてお知らせくださると、なお助かります。
※ 原稿内容について、編集とのやりとりが発生することにつき、ご了承ください。
(4)進呈
寄稿いただいた方には、新刊本誌を進呈(※ 進呈冊数は2を予定)させていただきます。
3、企画趣旨
(underconstruction)
アニメクリティークvol.5.5 「新海誠/君の名は。特集号」発刊告知 #bunfree #anime_critique
2016.11.14 書影案(表紙案)更新


『君の名は。』特集号を発刊します。寄稿者等計15名参加、記事数は22本予定です。
以下の通りです。
1、コンテンツ
1.) 『君の名は。』読解・解説・批評・評論等 ×11本
2.) 『君の名は。』コラム ×4本
3.) 追録小説『君の名は。』 ×7本
※ 各評者による自身の評論+『君の名は。』への導入となるショートショート
4.) イラスト (作成中)
※ 東京文フリ11/23(水・祝日)頒布
※ A5, 100ページ: 頒布価格600-700円予定
2、寄稿者・参加者
1.) contributor.
@WataruUmino , @wak , @totinohana , @tackerx , @SpANK888 , @narunaru_naruna , @Mrbitss , KH, @kei_furuto , @frenchpan , @diecoo1025 , @deyidan , @burningsan , @AmberFeb201
2.) illustrator.
@yopinari , @konkatuman
3.) editor.
@Nag_Nay
3、sample. 追録小説
i.) かつて敗れていったツンデレ系サブヒロイン (@wak) | Twitter

ii.) なーる (@narunaru_naruna) | Twitter

iii.) バーニング (@burningsan) | Twitter

iv.) 偽うみのわたる@文フリ東京 カ-39 (@WataruUmino) | Twitter

v.) ねりま (@AmberFeb201) | Twitter

vi.) すぱんくtheはにー (@SpANK888) | Twitter

vii.) tacker10 (@tackerx) | Twitter
(under construction)
4、sample. 評論等
i.) かつて敗れていったツンデレ系サブヒロイン (@wak) | Twitter


ii.) ぱん (@frenchpan) | Twitter

iii.) K.H.


iv.) 古戸圭一朗@3日目東U24a (@kei_furuto) | Twitter

v.) バーニング (@burningsan) | Twitter


vi.) 香川に行ったあんすこむたん(旧でりだん) (@deyidan) | Twitter

vii.) なーる (@narunaru_naruna) | Twitter


viii.) ねりま (@AmberFeb201) | Twitter


ix.) すぱんくtheはにー (@SpANK888) | Twitter


x.) Dieske (@diecoo1025) | Twitter
(under construction)
xii.) tacker10 (@tackerx) | Twitter
(under construction)
xiii.) (No name)
(under construction)
評論・コラムは、『君の名は。』に関する読解・解説・批評・評論等を含む。
その直後に挿入されている追録小説は、各評者による自身の評論+『君の名は。』への導入となるショートショートとして補録された。なお、TwitterにおけるSS例を念頭に 140×6字=840字 の制限の下、執筆を依頼している。
なお、本冊子は、アニメクリティーク vol.5.0 「アニメにおける資本・文化・技術/不条理ギャグアニメ」 特集号(近刊)との連関を意識して作成した。アニメ制作工程にあらたな潮流を導入した製作者としての新海誠の顔とともに、アニメクリティーク vol.5.0をあわせて参照されたい。
以上
------------以下、公開時 8/27 における寄稿募集文など
1、刊行趣旨:寄稿募集に際しての若干のメモ
2013年10月のたそがれ時、自らの片割れに逢いに行くために、彼女(の身体をした彼)は疾走する。しかし、自らの片割れに出逢ったがために、彼女は「あの人の名前が思い出せないの?」(=「彼は誰?」)と叫ぶことにもなる。というのも、そもそもたそがれ時に逢えるのは、この世ならざるものであり、此岸と彼岸との距離を隔てたものだからだ。
・・・
ではなぜ彼女は、現実には不在である存在を思い出すことができるのだろうか?
忘れてしまった何か・何処か・誰かを覚えていられるというのは、それが錯覚でなければ、一体どのようなことなのだろうか?
あるいは、現実に生きる私たち視聴者は、同様に知らない者を記憶し、知らない者の名を呼ぶことは(オカルト的な意味ではなく)本当にできないのだろうか?
(1) 『君の名は。』:集大成/新境地としての二面
1−1: 連続性
上記のたそがれ時を跨いだ場面には、既存の新海誠作品と『君の名は。』を繋ぐ時間的遅延・空間的距離のモチーフが現れている。
作中で述べられているとおり、たそがれ時は彼岸と此岸を繋ぐ時間であり、世界には存在しないはずの魔に逢うことのできる場である。そこで彼女は、彼女の世界には存在しないはずの彼に出逢う。山を降りた今や名前も思い出せないけれども、自分の「半分」をなしていた誰かに彼女は確かに出逢った。その記憶だけが、彼女の今(作中2013年10月)の衝動を支えている。
・・・
物理的な距離を隔ててなお自分とはもはや決して分離できないくらい距離が近づいた他者、下手をすれば何年何十年と不意に記憶を苛み続ける確固とした他者のモチーフは、『秒速』や『ほしのこえ』でそうであったように新海誠作品を要約する時の一つの常套句として通用するものと思われる。
実際、本作においても、「あの人の名前が思い出せんの!」と叫ぶ忘却の直前、爆破シーンにおいて勅使河原との会話で「(「ごめんやって」て)私が!」と述べていたのは、その片割れは「私」と未分の他者だからである。そんな他者がいた確信すら残らない過去の引っかかりとともに、大人になった今(作中2021年時点)でもまだ、彼女は自らをそんな誰かに投じ続けている。
だからこそ作品冒頭、美しい街の風景を背景とした「気づけばいつものように」「私は誰か一人を、一人だけを、探している」という二人のモノローグの重なりは、既存の新海誠作品を想起させるに相応しい場面の一つであるだろう。
1−2: 断絶
そんな既存作との連続性に対する予感を裏打ちするように、彼女たち二人をつなぐ携帯電話というガジェットは、いつもの通り不通である。相互通話は不可能で、互いの携帯に入れたアプリ(オンラインストレージ上)にメモを保存しておくことができるだけだ。この、2つの一方通行のコミュニケーションもまた、新海誠的であるとされやすいかもしれない。
・・・
しかし、ここで既存作との一つの断絶が走る。というのも、この不通はいつもどおりの設定考証にとどまるものではないためだ。
本作においては、携帯電話は最初から一度たりとも通じたことがない。そのため、彼女たちは、かつて通じ合った(と相互に信じた)関係の不在に縛られているわけではない。つまり、携帯電話の不通は、(不通の)ガジェットが表していた過去を表す物ではない。この点で、過去の呪縛に焦点が当てられていた既存作とは一線を画する。
本作で彼女たちは別の仕方で繋がっている。例えば、糸守町の風景画によって、油性ペンで引かれた名の痕跡によって、名でさえない衝動を伝えるだけの「好きだ」の文字によって、そして何より形に刻まれた意味や歴史を失ってしまった遺物たる組紐によって。
もちろん、名前ももたないただの線の痕跡など、結びつけられるべき場所を持たず、容易く失われてしまう。脳状態に書き込まれなかった記憶が保持しえないように、あるいは現実との整合を持たない夢は、夜を明かせば早晩(いつか)消えてしまうように。それでも彼女たちは、決して現実にはありえなかったはずの記憶の場所を手繰りよせようともがき続ける。満員電車から身体を押し出す際の自動ドアもまたある意味でそうであるように、引き戸を(手前側ではなく)奥側に開け放つ時、彼女たちは自らを焦燥とともに世界に押し出している。
1−3: 喪失の記憶、喪失されつつある記憶
このようにして考えていくと、時間的遅延・空間的距離という常套的なモチーフとは異なり、本作にはもう一つ、新たなモチーフが読み取りうるかもしれない。そのモチーフとは、「喪失の記憶」というモチーフである。それは、何かを失ったという喪失の記憶であるとともに喪失されていく記憶であり、失ったものが何なのかさえ忘れてしまう喪失の記憶である。「忘れちゃだめな人」を忘れてしまう喪失であり、記憶が絶えず薄らいで、幸福な時間が絶えず失われてしまう世界を忘れてしまう喪失である。
・・・
作中に「今はない景色」という言葉がある。それは、よく描けているかつて在りし牧歌的な糸守の景色であるとともに、「東京だっていつ消えてしまうかわからない」カタストロフの悲劇の風景でもある。これらの景色は、しかし実は常に一つである。美しい景色は次の瞬間、突如として悲劇の中に落ちて消えてしまうかもしれない。むしろ、悲劇が悲劇として理解されるからこそ、記憶は容易く埋没し、風化してしまうのかもしれない。例えば図書館に山と連なる本の中に埋もれてしまうように。
喪失の記憶を強調する本作は、確かに糸守の悲劇を「夢のように美しく」に描いている。しかし、その美しさに魅了されるだけで背景世界にアクセスせず、過去の記憶を反復することに拘泥していたならば、既存作品における背景美と変わるところはなかっただろう。本作では、彼女たちは背景に介入する。幻想的な美しさの中にあった残酷さに対して抗うことにこそ、彼女たちは衝動を持つに至る。
美しいのは、背景の美しさに抗い、美しさの中にある(妄想にすぎないかもしれない)歪さへの衝動を持つ彼らである。(その点では必死な滝について放っておけないという奥寺先輩のセリフは、我々視聴者の視線を先取りしているのかもしれない)。
・・・
もちろん、その衝動さえも、大人になってしまえば容易く失われてしまう。彼らはもはや2013年の出来事の当事者ではないし、ほとんどすべてのエピソードを忘れている。そうして忘れ去って誰しも大人になり、衝動を失った今(作中の2021年)になってみれば、奥寺先輩の言うように「君も幸せになりなよ」と言葉を投げかけることは容易にできる。できる、のだろうけれど、それでも幸せが何かを知るには誰もが多くを忘れすぎているのではないかという思いに、彼女たちはとらわれざるをえない。
私の片割れを、たそがれにおいて、それと意識することなく、「いつ失われるかもしれない」都市で探さざるをえない。これは呪いだろうか?祝福だろうか?
(2) フィクションを通過するという「ヒジョウな幸運」?
さて、以上のような長々しい本作のパラフレーズは、オタク的な妄想だろうか? あるいは新海誠による呪いのようなものだろうか?
そうではない、と筆者は感じる。これは非常な幸運なのだと筆者は信じる。
流れ、つまり「ムスビ」を保持することは苦しい。知っているはずの通学路を知らないかのように振る舞うこと、知っている人を知らないかのように取り扱うこと、忘れちゃいけない人に忘れたかのように出会うこと、自分の名前を知らないかのように返事をすること、そして「まだ知り合ってないのに(名を呼んで)会いに来る」こと。これらはどれも不合理で、現実にそぐわない振る舞いで、フィクションでしかありえない。有り体に言えばそのフィクションは(勅使河原のいうmulti-verse並みの)オカルト的妄想にすぎない。
それでもこんな妄想は、現実でしかない他者との間では辛く、まだ見ぬ(虚構の)他者との間では「大変な幸運」なのだ、と言うのが、本作から読み取りうる寓意であると筆者は信じる。
・・・
たとえその妄想が非情なカタストロフの希求であったとしても、その世界が美しいと思えるのは、絶えず失われつつある何かへの衝動を呼び起こさせるからだ。そして、何かに取り憑かれたかのように、既知の事実を掘り起こすのは、そこに「今はない景色」、つまりかつてあったかもしれない景色や未だあったことのない、尋常ならざる景色を重ね合わせてみることができるからだ。
こうして黄昏の妄想は終わりに抵抗する。終わりが始まることにも、終わりが終わることへも抵抗する。名を呼ぶことで既知になる何かに抵抗している。
・・・
「君の名は。」の句点もまた、「君の名は(宮水三葉)」と呼ばれてしまうことへと抵抗している。命名儀式に対して抵抗している。すでに知り合った既知の人を、名前なしに呼ぼうとする衝動だけが、その言葉にまだ滞留している。
映像そのものは「君の名は。」に始まり、「君の名は。」で終わる。そのラストが、その句点の手前に留まったことは必然である。
・・・
筆者はここにフィクションのキャラクターの救いを見る。彼女たちは自らの片割れの名を知らず、現実の我々以上に片割れに出逢い損ねている。私たちがフィクションを既知のものとするより先に、彼らはフィクションの側に進んでしまう。
それでも彼女らが幸運なのは、その名指しえないフィクションを真に受けることができるからだ。その不合理な衝動こそが、現実に生きる私たちにとっては「今はない景色」である。
だから我々視聴者もまた、フィクションを現実的な形で思い起こさねばならない。フィクションの中に閉じこもるのではなく、より多くのフィクションに身をさらさなければならない。そしてより多くのフィクションを通過して、より多くの景色を眼差さなければならない。
そう信じつつ、以上を刊行趣旨としたい。
(3) 寄稿募集
そんな救済をめぐる物語として、私は『君の名は。』を観た。そこに既存の新海誠作品との断絶をも見た。しかし、この見方については異論も予想される。例えば次のようなものが一案としては考えられよう。
・そもそも新海誠を論じるにあたっては、映像をこそ(あるいは『ほしのこえ』以降からほぼ全作にわたって続く映像の作り方の変化をこそ)論じなければならないのではないか?
・本稿冒頭にある疾走にしたって、運動表象として論じなければ手落ちなのではないか?
・あるいは、主観ショットが三人称のショットに移り変わる定位置回転の構図こそが、彼女たち二人のストーリーラインと画面との照応関係に立っているのではないか?
・既存の新海誠作品との連続性をむしろ強調すべきではないか?「失われつつある記憶」のモチーフは、『秒速』以来の十八番ではないか?
・あるいは、もはやMVを思わせる挑戦的な音楽の導入については触れなくてよいのか?
などなど、ざっと思いつく異論反論はこのようなものが挙げられるだろう。
・・・
編集側としてはいずれも尤もだと考える。それとともに、問題だと感じるのは、これらの問いを整合的に掛け合わせ、蓄積する場所が(少なくともWeb上では)僅少なことにある。そもそも統合思考に乏しいツイッターは時とともに流れさってしまいがちだし、思い出して見返そうとした時の一望性にかけるきらいもある。何より、著者たち相互の間で意見をぶつけ合う場の設定が、なかなか困難になりがちな点も指摘できるかもしれない。
可能ならば、弊アニメクリティーク誌が(実際既刊の編集過程で意見照応をさせ、可能ならば本誌に反映させてきたように)意見を闘わせる場所になれれば、と考えている。アニメクリティーク誌は、次号『アニクリvol.5.5_β 新海誠/君の名は。』特集を文フリで無事出すことができれば、丁度3年目を迎えるとともに、計9冊目の刊行となる。長い間弊誌を支えてくださった寄稿者諸氏・読者諸氏に改めて御礼申し上げるとともに、広くご協力を仰ぎたい所存である。
以上を踏まえ、各人それぞれの観点を伴った論争的な寄稿文を、以下の要領に従い募集したい。
2、寄稿要領
(1)発刊趣旨
以上の通り。
(2)装丁・発刊時期:
オフセット印刷、A5、60頁程度で企画しています。
発刊時期は、2016年秋の文フリ(11月)を想定しています。
(3)募集原稿様式
a. 文字数:
①論評・批評 : 3000字程度から15000字程度まで。
②作品紹介・コラム:500字程度から2000字程度まで。
b. 形式
.txt または .doc
c. 締め切り
第一稿:10/1
(※ 早めが嬉しいです。ただ個別に連絡いただけましたら延長することは可能です)
(※ その後、何度か原稿の校正上のやり取りをさせていただけましたら幸いです。)
最終稿:11月上旬
d. 送り先
anime_critique@yahoo.co.jp
※ 参加可能性がありましたら、あらかじめご連絡いただけましたら幸いです。その際、書きたい作品、テーマ、内容についてお知らせくださると、なお助かります。
※ 原稿内容について、編集とのやりとりが発生することにつき、ご了承ください。
(4)進呈
寄稿いただいた方には、新刊本誌を進呈(※ 進呈冊数は2を予定)させていただきます。
以上
すぱんくtheはにーさんの評論冒頭
さて、コミケ期間限定で、すぱんくtheはにーさんの評論冒頭1節+αを紹介します。
「ガルパンがないぞ」という話は無しで。第2節でちゃんと出てきます。あと3節はカオスですが、読ませるものになっています。話としては『アニクリvol.4.0』のすぱんくさんの論に続くもので、そちらをお読みくださると理解が進むものと思われます。(例によって簡潔な紹介で申しわけありません)
本誌においては、本論考に続いて、@tackerx さんと、@totinohana さんからのレビュー、そして 、@SpANK888 さん自身によるリプライが掲載される形となります。
以下、抜粋となりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
-------------
1 Kickstart My Life
(1)Kickstart the life, but whose?
『ばくおん!』最終話において、主人公・佐倉羽音は「バイクでいままで一度もコケたことがない」と述べた。それに対し、バイクに乗ることを勧めた天野恩紗は羽音へ向けてこう告げる。
「バイク乗りってのはコケて初めて一人前になる生き物なんだからな」
この一言は事もなげに投げかけられるが、一見すると逆説的だ。
なぜなら、想定している/されているライディングを行う限りバイクはコケないためだ。決められた挙動の中では、バイクはコケることはない。ならば、普通に考えれば、「コケない」ことが一人前の証明なのではないだろうか?バイクを上手くコントロールすることで「コケない」ことが一人前の証になるのではないのだろうか?
しかしそうではない。
ここには、虚構のキャラクターが「決められた運動」から逃れ、予想を逃れるという意味において初めて実在する「生き物になる」過程が、如実に示されているためである。
(2)Kickstart “My” Life
バイクをコントロールする機構は両手と両足にしかない。しかし、その四ヶ所だけで「バイクに乗る」ことは
できない。自立できない乗り物であるバイクはライダーの支えなしでは真っ直ぐに走ることすらかなわなず、曲がり角では操作機構には存在しない、車体ごとライダー自身の体を傾けるという挙動によって初めて曲がることが可能となる。
全身をフルに使いながら「想い通りのライン」を走っていく快感はバイクの大きな魅力の一つだ。
そしてその快感は「ダンス」に似ている。
手足の挙動を越え、ステップし、全身を動かすことで「想い通りの振り付け」を描く。全身で「イメージする身体」を表出させる快感は、バイクとダンスに共通する”喜び”である。
しかし同時に「想い通りのライン」「想い通りの振り付け」は、「決められた動作」をライダーに強要していく。そういった「決められた動作」として印象的なものに、アニメにおける「バンク」システムがある。変身や合体、あるいは必殺技といった「重要でありながら決まった動作を行う」シーンを、銀行(バンクbank)に預けるように保管し再利用するために引き出すシステムである。
それは「バンク」シーンの度に、同じ映像を画面に描く。それは正に「思い通り」の動作を常に、完璧に描くことができるシステムであり、ある種「思い通りのライン」「思い通りの振り付け」の完成形であると言える。
それは何度でも何度でも、同じ動作を「再現」することができる。しかしそれは先に述べたように、決められた運動から逃れられない「虚構」であることを強く要請するものでもある。
一方でバイクも「バンク」を行う。バイクはカーブを曲がるときその車体をライダーごと斜めに傾むける(バンクbank)することで旋回性能を得る。その瞬間に「思い通りのライン」が要求するバンクの角度は一つしか無いのかもしれない。だが路面の状況や、道路の混雑状況、マシンのコンディション、あるいはライダーの精神状態によって「思い通りのライン」は変化し、同時に「バンク」の角度も変化していく。
同じバンク(bank)という言葉を持ちながら、アニメにおけるそれは「決められた動作」を繰り返すものであり、バイクにおいては「一度しか現れない」ものだ。
その一回性によって変化する「バンク」は常に異なった結果をもたらし、それは時としてバイクがコケる可能性を開いてしまう。そしてコケるがゆえに、その挙動は「決められた動作」から逃れることを可能とするのである。
つまりコケることができないバイク乗りの姿は可変する「バンク」ではなく、不変の「バンク」によって「決められた動作しかできない」虚構的存在となってしまう。
……つまり恩紗のセリフはこう言い換えられる。
「バイク乗りってのはコケて初めて生き物になる(傍点:生き物になる)んだからな」
(3)Kickstart their life
過去、『アニメクリティークVol.4』の拙論では、アニメにおけるアイドルのダンスを例に、次のように述べていた。『アイカツ!』における大空あかりの「ダンスの失敗」は、ダンスが持つ規定された動きから外れるものである。それゆえにキャラクターを「決められた動作しかできない虚構的存在」から「予想外の動きをする実在的存在」へ変化できる一つの回路として働くものだ、と。
この理路は、一見すると捻り過ぎで蛇行しているように見えるかもしれない。拙論以降のアニメ表現としても、例えば『プリパラ!』では、ガァルルというダンスの習得をはじめたばかりのキャラクターがライブを行い、そのステージ上でアイドルとしては未熟なガァルルは「転倒」する。つまり、大空あかりもガァルルもアイドルとして未熟である表現として「ステージ上での転倒」が描かれ、コケることが一人前ではないことの表現となっているためである。
しかし、ここでは実は、コケるのはアイドルとして未熟だからだ、という意味自体が「転倒」しているのだ。
(引用はじめ)
「死なない身体」を持つアイドルから、「殺せる身体」を持つアイドルへ。もはや決して取り戻せないもの(典型的には死の可能性)を与えることによって、もともと死んでいたはずのキャラクターは、はじめて生を得ることができる。(『アニメクリティークVol.4 Dance of the Dead——自然主義的フィクショナリズムと、殺せる身体の行方』より)
(引用終わり)
バイクはコケて傷つくことによって、取り戻せない欠損を得る。ダンス中にコケることによって、取り戻せないステージの失敗を得る。それは「死なない身体」から「殺せる身体」への移行である。絶対に傷つかないバイクから傷つくバイクへ、虚構的存在から実在的存在への変化がここでは起きているのである。彼らはここで彼らにとっての「私の生」を駆動させている。
それは私たち現実の身体と、キャラクターたち虚構の身体の境界がまるで取り払われたかのような錯覚を覚えさせる。そしてその瞬間、私たちの現実は虚構によって上書きできる可能性が開かれるのだ。
虚構がフィクションが、現実に生きなければならない私たちの世界を豊かにするためには、この境界の「混乱」によって現実と虚構を等価に繋ぎ止めなければならない。
この虚構的存在から実在的存在への変化だけが、それを可能にするのである。
2 その鼓動さえも暖かい
(1)突発的な写実--『ばくおん!』
バイクがコケることが、なぜバイク乗りを「生き物」にするのか。ここで、虚構の存在が実在の傷を負う可能性を先鋭化した作品として、もう一つ『ガールズ&パンツァー』を上げることができる。
『ばくおん!』最終話では、上記の会話のあと羽音がバイクを初めてコケさせてしまうシーンが描かれる。駐車状態からバイクを倒して傷をつけてしまうのだが、このとき羽音の顔には特徴的な「歯」が描かれている。
『ばくおん!』全話を通してこの歯の描かれ方がされるのは、この1シーンのみだ。さらに、通常描かれる歯の表現よりも写実性を持った描かれ方がなされている。
アニメの中のバイクが傷つき、実在的存在になろうとするその瞬間に、羽音の口にも写実的な歯が出現する。この含意は何か?
そもそも鉄の馬とも形容されるバイクは、人馬一体としてライダーとの身体的結びつきを強く要請する乗り物だ。二輪車の教習ではこのように言われる。「バイクは見ている方向へ曲がっていく」と。バイクに跨った状態での視線の方向は、自然と体に傾きを与え、その傾きによってバイクは自然に視線の方へ曲がる。
この意志と動作と挙動の一致は、ライダーとバイク本体との境目を曖昧にしていく。まるで自分とバイクはこの跨った状態が本来あるべき「私という生き物」の姿であるかのように強く錯覚させられていく。キックスターターを蹴ることによって、「私」は初めて自分の輪郭を拡張し、生(My Life)の実感を得る。
ここから、バイクの傷とは、ライダーにとって延長された自分の身体に与えられた傷となる。だからこそ、バイクが傷つく=実在的存在になるとき、ライダーの身体には写実的な歯が現れ、バイクと同時に虚構的存在から実在的存在への移行が起きるのである。
(2)必随する傷--劇場版『ガールズ&パンツァー』
-------------
(以下略)
以後、2(2)が続いたのち、
3 伝えるべきもの
(1)身体の消失点の〈彼方〉
(2)死ぬことのない死体を見るのか?生くることなき生を見るのか?
(3)乗りと勢いの国は此処に
と、バイク乗りならではの叙情的な一節で文章はしめられます。
なお、橡の花さんとtacker10さんからのコメント(とリプライ)については、すぱんくさんに関する様々なネタバレを含むのでこちらでは省略ということで。
以上
tacker10さんの評論冒頭(抄録)
さて、コミケ期間限定で、tacker10さんの評論冒頭1節(といっても7000字超ありますが)を紹介します。
これは『アニクリvol.4.5_β ガルパン総特集号』の第1章の基調となる「アニメにおける輪郭線と音」についての論考です。(本来ならここで編集側での概説を加えるべきでしょうが、あくまでも紹介につき、今回は省略するということでどうぞよろしくお願いいたします。)
本誌においては、本論考に続いて、@totinohana さんと、@yokoline さんからのレビュー、そして 、@tackerx さん自身によるリプライが掲載される形となります。
以下、抜粋となりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
------------------
0.はじめに
二〇一二年放送のTVアニメ『ガールズ&パンツァー』第一話「戦車道、始めます!」冒頭シーン、隊列を組みながら前進して行く敵軍を捉えた戦車の一人称視点とも言うべき画面に、二人の少女が身を潜めて喋る声が何処かから聴こえて来る。
「マチルダⅡ四両、チャーチル一両、前進中」
「流石、綺麗な隊列を組んでますねえ」
「うん、あれだけ速度を合わせて、隊列を乱さないで動けるなんて、凄い」
「こちらの徹甲弾だと正面装甲は抜けません」
「そこは、戦術と腕かな」
「へへっ、はい!」
我々は、その声が果たして誰の発した音なのかを画面に探す。しかし、この時に音源となるはずの二人は画面に存在せず、喋り声は誰のものでもない「フレーム外の音」として反響する。代わりに、まさに描かれている砲台の如く声の主を探して画面上に向けられた我々の視線=照準線は会話の対象となっている戦車の隊列を発見する。つまり、画面上を彷徨う声は、その主ではないが、会話の対象となっている遠景の戦車の姿に己が落ち着くべき居場所を得ているのだ。
そこから、すぐさま画面上には輪郭線を基本に描かれた二人の少女が現れる。崖下から駆けながら偵察から帰還したらしき二人は、一方がそのまま戦車をよじ登って画面手前へ消えて行くのに対し、もう一人は画面内に留まって、操縦席に手を伸ばして車中の人物を起こす芝居を見せる。それと同時に、画面には「麻子さん起きて。エンジン音が響かないように注意しつつ展開して下さい」という先程と同様の声が与えられていることで、つい先程までは「フレーム外の音」だった喋り声が、映像におけるキャラクターと声の芝居のシンクロによって、今度はいままさに画面内に映る少女から発された「インの音」として鑑賞者に理解される。そして、それまでは遠方を進軍する戦車の隊列に視線を促しながら彷徨っていた声が目の前に自身の宿るべき主を見出されるのに伴い、我々の意識もまた、遠景から近景へダイナミックに運動するのだ。
このようにして、作中で最初に画面上を彷徨う声の主という大役を戦車から受け継いだ彼女こそが本作の主人公、西住みほである。
このシーンが端的に示す通り、「映像作品」において画面上の音はミシェル・シオンが『映画にとって音とは何か』で定義した「イン/フレーム外/オフ」の境界を筆頭に様々な隙間を、さながらどのように困難な場所も踏破する戦車のように軽々と踏み越えて行く。例えば、先述した場面、画面内で発されたみほの「麻子さん起きて下さい」という声は、実際には描かれてはいないものの車中に存在するであろう呼び掛けられた対象としての「麻子」というキャラクターを画面外の余白に生じさせながら、その「みほ」と「麻子」という異なる輪郭線で区切られた二人の人物の隙間を越えている。キャラクターを境界に囲まれたある種の枠(フレーム内フレーム)であることを考えれば、会話もまた、人物のフレームからフレームへと声が境界を跨ぐことに他ならない。
翻って、アニメーションにおける輪郭線には、先程の場面で「麻子」を眠りから起こすための線で描かれた芝居に声が同期することで、かつて「フレーム外」を漂っていた声が西住みほというキャラに吹き込まれる(「イン」になる)かのように複数の線で描かれたコマ毎に異なった形のキャラクターをキャラとして結集させると共に音の在り処を即座に同定させる力がある。しかも、運動の方向は、外から内のみではない。アニメーションに特殊な輪郭線は、何処まで行っても仮初であり、それ故に音源の一意性を越え出て行く。よって、画面の中に一旦は位置付けられた音も、まるで鳥たちが止まり木で羽を休めた後に再び力強く羽ばたいて行くかのようにその輪郭線から、次のコマ、次のカットという新たな空間へと形を変えながらより力強く運動して行く。再び冒頭シーンで説明すれば、偵察から帰還した二人が画面の手前に消え、同時に「麻子」を起こすみほの声によって、画面の手前にはみほの指示する「展開」を行うだけの余白が既に充分な形で伸びている。その余白に対して実際に画面は「展開」され、その中をまた声が渡って行くことで画面は(同時に我々の意識も)運動して行く。
そもそも文芸、音、映像、舞踏といった諸技術は各々が独立した空間認識と時間認識を持つ。それらの形式が折り畳まれた複合芸術であるアニメにおいては、それぞれの要素が複数のリズムでお互いに介入し合いながら映像内外に伸縮する広い空間への運動を生んで行くのだ。
以上を確認した上で、本稿では、アニメ『ガールズ&パンツァー』シリーズにおいて、主人公の西住みほが自由に動き回ることの出来る大洗女子学園戦車道チームという開けた空間=充分な余白を得ることで本来の大胆さを発揮して行った姿に注目する。
そうすることで、同作が先述の境界を踏み越える音の特性への自己言及的な内容を展開して行く点を捉えるためである。
そして、その自己言及が行き着く先に、もはや声が台詞自身すらも必要としなくなった臨界点としての異なる声が自由に共存し得る場である輪郭線まで辿り着き、アニメという媒体を捉え直すことが本稿の目的だ。
では、実際に本編の内容に踏み込んで行こう。
1.繋がる輪郭線、共有される声
(1)戦車から大胆に飛び降りること
アニメ『ガールズ&パンツァー』の主人公である西住みほは、元来非常にアクティブな性格の持ち主だ。それは二〇一五年に公開された映画『ガールズ&パンツァー劇場版』で挿入される回想シーンに描かれた彼女の幼少期の姿を観れば一目瞭然である。
何処までも広がる畔道を走る戦車上で、幼少期のみほは目を輝かせ、自由に飛び回る鳥たちに飛び跳ねながら手を振り、戦車を降りる際にも姉のまほが差し出した手にかぶりを振って自分の力で飛び降りようとする。眉の動きや頬の高潮に現れているように、彼女の表情は感情表現も豊かに描かれており、年齢の割には既に落ち着いた描写の姉とは極めて対照的である。
しかし、前述の回想シーンから数年後の時点となる、『ガールズ&パンツァー』第一話「戦車道、始めます!」で県立大洗女子学園に転校して来たみほにその溌剌とした面影は全くない。寧ろ、どちらかと言えば気弱で、引っ込み思案なタイプという印象に描かれている。
それにもかかわらず、実際には彼女こそが後にこの弱小高校の大洗を率いて戦車道全国高校生大会優勝を果たすのである。
それも第一話の印象から思いも寄らない大胆な作戦を用いて。
故に、ここで重要なのは、彼女の立てる作戦の大胆さが、元来彼女が持ち合わせていたアクティブな性格の発露であったと劇場版で捉え直されている点だ。当然のことながら、映画『ガールズ&パンツァー劇場版』が『ガールズ&パンツァー』の後から制作をされた作品で、みほの幼少期の挿話も事後的に追加された描写であることからすれば、「みほは大洗女子学園で変わったのではなく、大洗女子学園において本来の大胆さを取り戻した」という仮説を立てることはそう不自然なことではない。事実、追加された回想シーンが、みほを(建前上)勘当した母・西住しほとの厳格な会話シーンの直後に置かれていることから考えてみても、みほが西住流・黒森峰女学園で自らに課された役割にきつく縛られ、西住の名に伴う重圧を背負い続けていたことを強調しているのは間違いないだろう。
そもそも、黒森峰を追われる原因となった戦線離脱もまた、回想シーンと合わせれば、役割の持つ閉塞性を否応なく強調する場面として解釈できる。回想シーンで、みほは戦車からの飛び降りに(姉の支えもむなしく)失敗するが、泥だらけになった二人は当たりも外れも区別がつかなくなったアイスの棒を見て笑い合う。「撃てば必中」(=必ず当たりを引く)を標榜する西住の名と役割を背負う前の二人は、その名に泥を付けることを厭わず己で決断して戦車から飛び降りるような大胆な行動を取り、例えそれが失敗したとしても結果に対して屈託なく笑いあうことがまだ出来たのである。そのような思い出が描かれた回想シーンが挿入されたことで、みほが取り戻すべきものが明確に示される構成になっているのだ。
つまり、みほに必要だったのは、自身の背負った重責を下ろし、かつてありし日に発揮していた大胆さを取り戻すことが出来るための環境だったのだ、ということをこのシーンでは再確認できるのである。
そして実際、第一話「戦車道、始めます!」は、彼女が大胆に動き回れるだけの環境を得るまでの物語を描いている。では、ここから実際に第一話の内容を確認してみよう。
(2)輪郭線を跨ぐ声
既に述べた通り、大洗に転校して来たみほは、それまで過ごして来た黒森峰での過去が原因で引っ込み思案な性格になってしまっていた。そんなみほだが、クラスメイトの武部沙織と五十鈴華に声を掛けられることで、次第に明るさを取り戻すかに見える。しかし、それも束の間、生徒会が戦車道の授業を履修するように迫ると、彼女の姿は同ポジに固定され、全く動かないままカメラに捉えられる(或いは、囚われる)。また周囲に促されて保健室に向かう際も、まるでその眼はゾンビのように虚ろになって、声を発する余裕すらなく、無言のまま立ち去ってしまうのだ。この一連のシークエンスで明確なように、転校当初のみほにとって戦車道とは未だ重く圧し掛かるだけの、自身の動きを阻害し、封じるものでしかない。
反対に、沙織や華と一緒に話す時には彼女の動きが大きく躍動していた(例えばみほが二人と喋りながら食堂で踊るように喜ぶ)ことは非常に重要である。何故なら、この時点から彼女たちがみほにとって自由に動き回るためのキーとなることの予兆が既に示されているからである。
そして事実、沙織と華こそが後にみほが大胆に動くための環境を得る契機となるのだ。
以下、更に詳しく見てみよう。角谷会長を筆頭とした生徒会の面々はみほを呼び出し、戦車道の履修を拒んだことを口々に責め立てる。この生徒会の面々に対し、沙織と華は、自分たちは戦車道を選びたかったはずなのに、みほを励ますかのように手を握りながら、怯えて黙り込んでしまっている彼女の代わりに弁護を行う。
そもそも、みほは戦車道が嫌いだった訳ではない。みほが避けているのは西住流戦車道であり、更に言えば、自分の心の赴くまま仲間一人すら助けることを許されないような、固定的に閉ざされた道の厳格さに他ならない。
そして、仲間を助けるために声を上げる沙織と華は、戦車道に異を唱えるのではなく、やりたくないみほに固定的な道を押し付けることに反対している。
だからこそ、ここにみほにとっての戦車道の転回が訪れる。そこで重要なのが、二人が行った代弁により、みほから発されるはずの声は自身の肉体という輪郭線を越え、異なる形に変形された輪郭線へと共有され、そこから発されたということだ。沙織と華の声は、一人の輪郭の内に閉ざされた空間を踏破する道(=余白)を切り拓いている。そのようにして沙織と華が切り拓いた新たな空間を得て一人の輪郭が三人の輪郭へと変形したことを契機に、みほの内に留まっていた声は溢れ出て、再び戦車道へとしかし西住流とは異なる形で戻ることを彼女は決意することが出来るようになるのだ。
そこから第一話終盤、戦車前で振り向いたみほを捉えるカメラが高速で引いて行くと、いままで彼女たちが過ごしていた空間が学園艦という巨大な船の上だったことが明らかになる。これまでの検討を踏まえるなら、このシークエンスの重要性は明らかだ。 みほは、かつて畦道を走り、そして飛び回ったような大胆さを、西住流の名と責任と共に限定され続けてきた。その西住流から逃れる術は、戦車道自体を離れるということしか、みほには考え付かなかった。しかし、今やそうではない。みほはこれまで背負い続けて来た重圧に押し潰されていた声を共有してくれる友人たちを通じ、いま再び大胆に動き回れるような環境を得た。そして、みほの中にある道はその新たな空間(=余白)の踏破を開始する。即ち、「装甲も転輪も大丈夫そう。これでいけるかも」というみほ自身の声が彼女自身の姿から戦車、戦車から倉庫、倉庫から学園艦へと引いていくその超ロングショットには、これから大洗の皆で作り上げるだろう新たなみほ自身の戦車道が重ねられるはずである。このカメラの運動によって示される余白の広さという環境こそが、みほが再び在りし日の大胆さを発揮出来るようになるために得られた環境に他ならない。
そして、そのような伸縮の余地を生む重要な役割を担ったのが、声と輪郭線の相互介入なのである。
(3)異なる次元の境界を渡る
こうして第一話では声が発されるための条件が描かれる訳だが、その点を踏まえてまず思い出したいのは、そもそもアニメのキャラクターが声を持たないということだ。我々に聴こえているのは、実際は声優に吹き替えられた声である。だが、それがキャラクターの発した声だと理解されるのは、キャラクターのイメージと声優により吹き替えられた声が共に与えられているからに他ならない。例えば、西住みほというキャラクターの声は西住みほというイメージと声優の渕上舞が揃うことではじめて機能するように。
まず、西住みほの声が成立するために、声優(の渕上舞)が必要であることは、誰でも容易に想像がつく。何故なら、平面上に輪郭線で描かれたキャラクターには具体的な発声器官が存在していないことを知っているからだ。
では、キャラクターのイメージのほうはどうか。
そこで、例えば『ガールズ&パンツァー』が存在しなかった別の世界を想定してみれば良い。その世界で、もしたまたま渕上舞が「パンツァー・フォー!」という台詞を発したとしても、そもそも西住みほというイメージが存在しない以上、それが西住みほの声だと認知されることはあり得ない。そして、その反対に、冒頭で触れた通り、画面に発された声が画面内に現れて芝居を見せる少女のイメージとシンクロすることで己の宿るべき主を見出されるに至ってようやく、西住みほの声が成立するのである。
即ち、キャラクターの声は、ある境界で区切られた、輪郭線で囲まれた器となるようなキャラクターのイメージを前提にして、その余白に声を吹き込む声優の身体という二つの輪郭線の境界(アフレコ方式で言えば、録音マイクを間に挟んだ声優と声を吹き込むべき映像が映し出されるスクリーンの隙間)を跨ぐことで動き出すのだ。
そうした意味で、みほの声にならなかった声が、みほと沙織と華の三人が手を繋いで、隙間を跨いだより大きな輪郭線に共有されることでようやく外へ開かれて行ったことと、キャラクターの声が機能する条件は相同的なのである。
そうして動き出した声を軸に、アニメ『ガールズ&パンツァー』シリーズはこれ以降、己を内に抑え込むのではなく、より開けた空間へ飛び出すような大胆さを是とする映像と音の特性を軸とした物語を展開して行く。視覚的に分かり易い例で言えば、大洗女子学園戦車道チームの面々が凝り固まった戦車のイメージへと囚われることなく、自分の好みにそれぞれの戦車を改造してしまうことが挙げられる。この大胆さは、戦車の起源が過去の第二次世界大戦の歴史にではなく、未だ余白である現在の彼女たちの戦車道にあることを示している。
その大胆さを用いて大洗女子学園戦車道チームは、例えばサンダースの通信傍受による進路の先回り、アンツィオのデコイによる足止め、プラウダの大軍による包囲といった、自由な運動を抑圧しようとする様々な作戦を打ち破って行くのだ。
特にプラウダ戦では生徒会チームが自分たちだけで抱えていた (これまた門戸を閉じることである)廃校の危機という大きな秘密を他のチームメイトにも共有することで、ようやく重荷から解き放たれることになる。
そして、隊長であるみほは、その重荷を引き受けつつも、活路を拓かなければならない必然性を、踊り(視覚)と歌(聴覚)に合わせてチームへと伝播することになる。
この場面は、一人で戦いの起源を引き受ける必要などなく、より広い空間へ共有されるように運動が開かれる(それこそが戦車道である)という軸に貫かれていることを端的に示してくれるだろう。
彼女たちが真にその重圧を共有する際に行うのが音に合わせて踊ることであるように、みほたち県立大洗女子学園戦車道チームの快進撃は音が新たな空間へと切り拓かれて行くことの追求と並行していたのだと捉えられるのだ。
2.コマとコマの間を越えて
(1)声優:コマに合わせすぎる不自由さ
そうして声優とキャラクターの境界を越えた新たな基盤を得て成立したキャラクターの声は、更に別の境界も跨いで越えて行く。それは、コマとコマの間だ。
そもそもアニメの画面はコマの連続であり、実際はコマとコマには間が存在している。しかし、その間を渡るように、声は各コマを貫いて踏破する。つまり、映像(視覚)と声(聴覚)の間には、必然的にズレが介在してしまうのである。
その際、日本で主にアニメと呼ばれる三コマ打ちの作画を基本とした作品では、映像と音声がズレて違和感を覚えさせないように、コマ毎の口パクにきっちり収まるよう演技をする高度な技術を必要とし、事実、声優はそうしたスキルを習得している。
しかし、ここで実は声優の技術力が高いことが問題になる場合がある。声優があまりにきっちりとコマにハマるように演技をし過ぎると、例えば会話の間が次第にアニメで主に使用される六、九、十二コマという間ばかりになってしまい、本来の会話にある多様性が失われてしまう可能性があるのだ。例えば、この問題に対して実際に言及をし続けているアニメ監督の松尾衡は、そうした多様性の喪失を避けることを目的の一つとして、日本のアニメで一般的に使用されるアフレコではなく、プレスコを採用している。 それは、この多様性の確保をスタッフだけの能力に頼るのではなく制作過程において実現するためだ。確かに、松尾が危惧するように、音が画面にただ追従するようにせせこましく窮屈に押し込められた演技になることは決して良くない。例えば、余韻を残すなどのために、台詞の言葉尻を次のカットに溢す演出をしたい際は、そのオーダーに対して大胆に対応して貰う必要があり、きっちりカットに収める演技しか出来ない場合では困るためだ。そのような演出のオーダーを理解し、臨機応変に対応することも声優に求められる能力である。ここには、声優と演出という制作過程における課題が露呈しているのだと言えよう。
(2)キャラクター:コマ間の臨機応変を映像内で実現する
そうしたアニメ制作における課題こそが、みほ率いる県立大洗女子学園と彼女がかつて在籍していた黒森峰女学院の決勝で描かれている。
そこで、大洗と黒森峰の試合展開を順に追ってみよう。
(以下略)
------------------
以後、2(2)が続いたのち、
3.複数の声が共存する輪郭線へ
(1)劇場版における定石と臨機応変
(2)リズムと共に再生される「らしい」戦い
(3)輪郭線と輪郭線の間
4.おわりに
で論はしめられます。
なお、橡の花さんとヒグチさんからのコメント(とリプライ)については、以下の通りです。
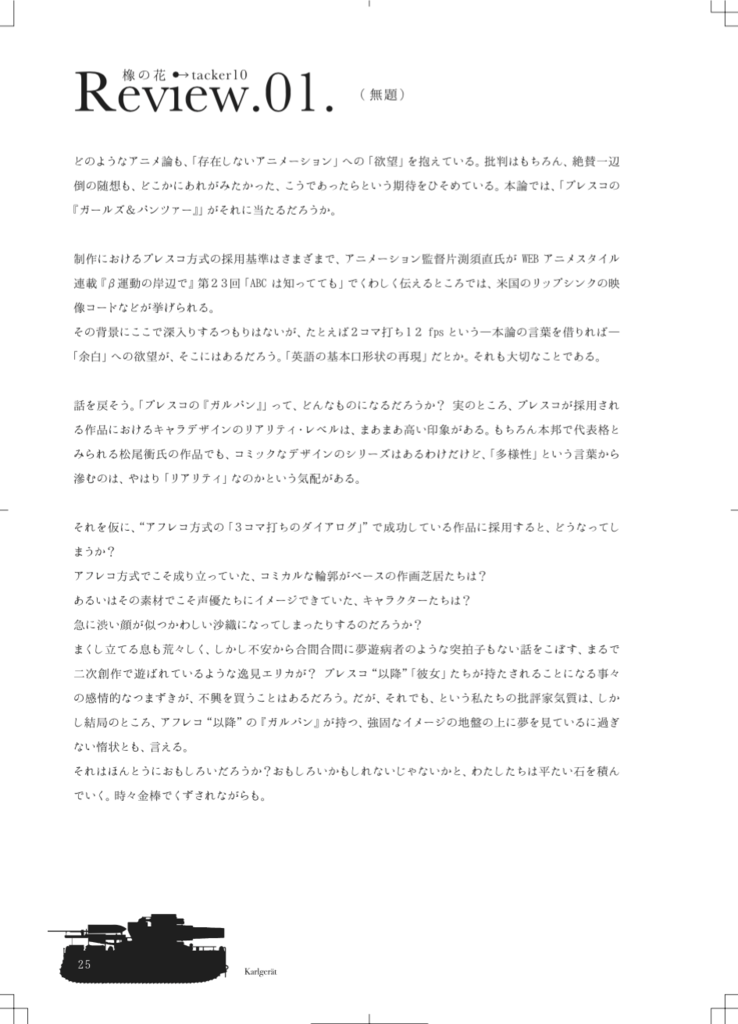
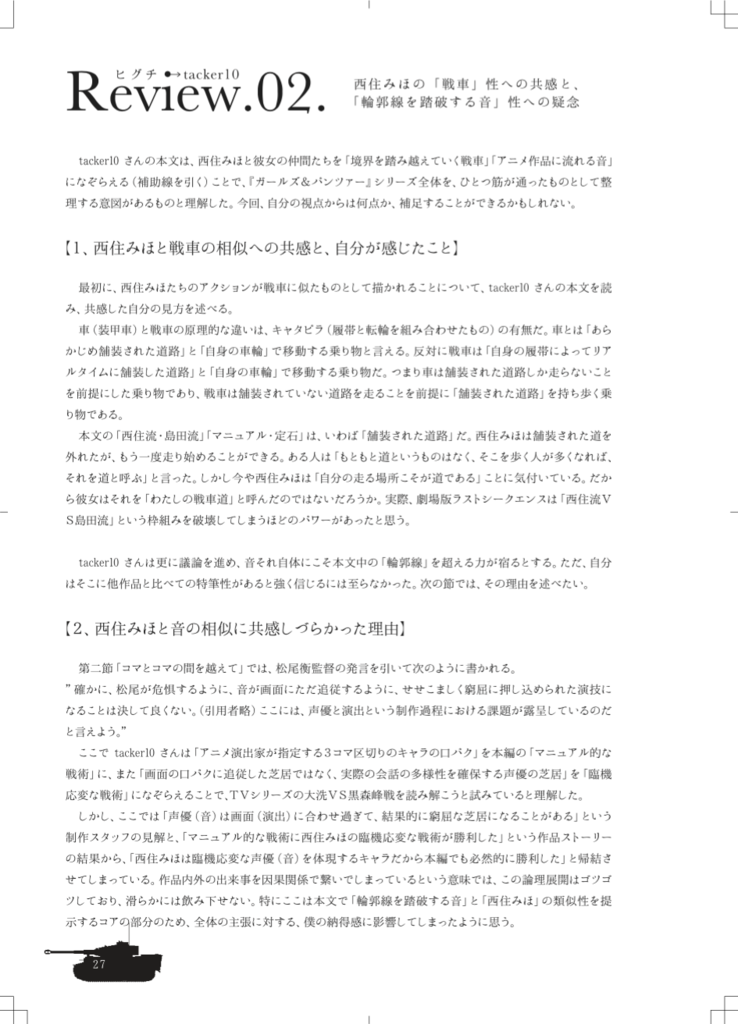

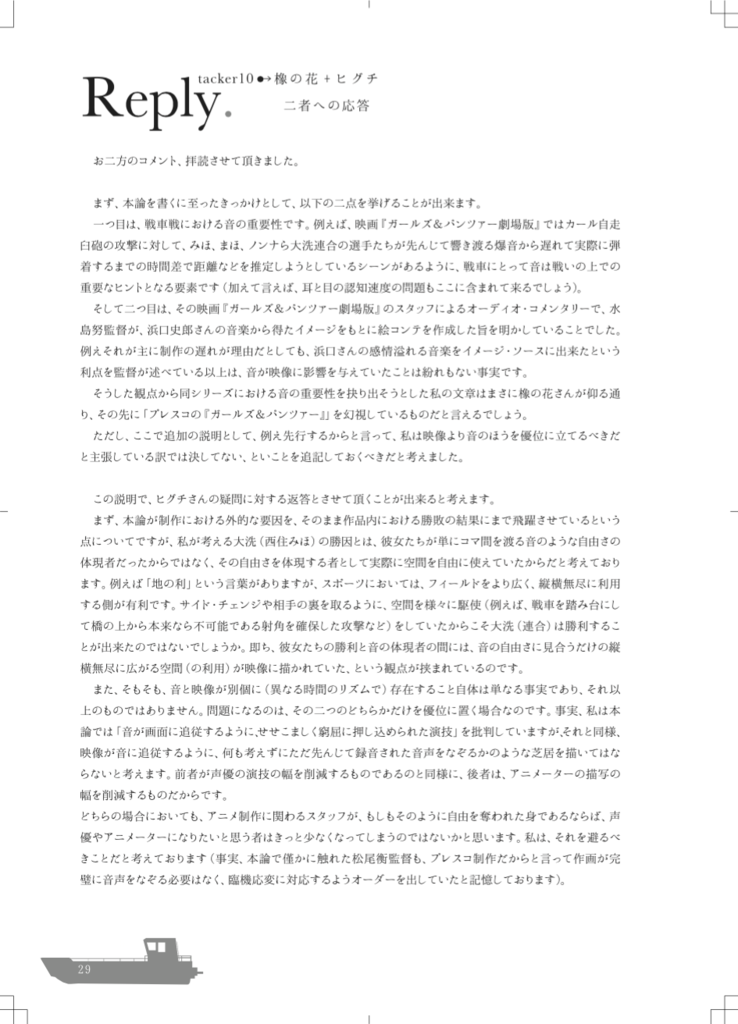

以上
PRANK! Vol.3 Side-B 水島努評論集 『おお振り』論 #C90
夏コミC90です。弊誌アニメクリティーク刊行会は3日目の東ポ15で配置されています。こちらについては別途リンク先の詳細を参照ください。試し読みもありますので是非。
さて、以下告知。
今夏は、いつものFani通( @fanitu )さんのところでほんの少しだけ評点をつけさせていただいたことに加え、久々にご近所の羽海野渉( @WataruUmino )さんのところで、水島努監督作『おおきく振りかぶって』についての寄稿をさせていただきました。
以下、内容紹介+冒頭公開+目次紹介です。
1、内容紹介
取り上げた対象作品は、ひぐちアサ原作・水島努監督作品『おおきく振りかぶって』です。
原作は野球漫画として珠玉の出来でありつつ、アニメ化に際して(漫画からの単なる引き写しではなく)巧みな翻案がなされた本作について、微力ながら整理を施させて頂きました。
本稿のモチーフはある意味では単純で「プレイヤーでも監督でもない、外野席の一観客として目の前にある運動(作品)を「みる」とはどのようなことか?」というものです。
事前にご相談に乗っていただいたねりま( @AmberFeb201 )さんからは、「作品論であるにとどまらず、スポーツ論/スポーツ観戦論でもあり、『おおきく振りかぶって』という作品のみならずアニメ/スポーツを視る、という経験をアップデートする、そういう論考」と、身にあまる要約をいただき、とても感謝しております次第です。
詳しくは、下記ねりまさんの『おおふり』記事にて。
いつもながらの丁寧な仕事で、私の寄稿文いらないんじゃないかと思うほどですが、是非両方見ていただけたら幸いです。特に、夏コミのある8/12-8/14は折よく甲子園の最中ですし、ぜひ本稿とともに「野球(運動/ゲーム)を見ること」についてご一考くださいましたら、筆者としては大変嬉しい限りです。
今回の原稿は、ねりまさんに加え、橡の花( @totinohana )さんやtacker10( @tackerx )さん、すぱんくtheはにー( @SpANK888 )さんにもご意見をいただきつつ、楽しく筆を進めさせて頂きました。機会をいただいた(+遅筆に寛大なご処置をくださった)編集の羽海野渉さんを含め、皆様に厚く御礼申し上げます。
以下冒頭抜粋+目次紹介です。
2、冒頭抜粋
0. 0'00"00 よき観客(spectator)とは何か?
(1)運動の芸術
第一話アバン。
ボールは綺麗に宙を二つに割って緩慢に上がり、落ちたボールの映像は長く止まる。絶え間なく動いている(はずの)ゲーム中の奇妙な間を経て、フレーム外から訪れる気怠げな足音とともに、ボールは遅延させられた送球でピッチャー・三橋の下に戻ってくる。戻ってくるショットだけは唐突だ。ぶつけないように声がけだけはされているが、三橋が振り返った時にはボールはもう目の前だ。切り返しなしでただ一人、ピッチャーだけが画面中央に残される。
鋭くピッチャーを眼差す内野、憮然とした表情でミットを外す外野、そしていつまで経ってもサインを出さない捕手。”彼ら”はおそらく、ピッチャーの「正確」なピッチングに慣れきってしまっている。「正確さ」に肉薄するために、三橋がどれだけ困難な過程(プロセス)を経てきたかも知ることなく。
しかし、「正確」なだけではまだ野球(ゲーム)にはならない。その意味で三橋はまだ野球(ゲーム)に参加していない。ただの「正確さ」は、相対する者との間の運動の可能性を減らしてしまうものだからだ。
だからこそここに、”彼ら”と対照的に、息遣い荒く視線を彷徨わせるピッチャーの逃げ場のなさが見て取れる。そうして読み合いなしに放られた球は、再度正確に宙を二つに割って、映像はフェードアウトする。かくして、フレームの間に滞留する、緩慢さと性急さが折り重ねられたリズムの不安定さに、まず冒頭で視聴者は酔うことになるだろう。
アバン終了。
・・・
水島監督自身が絵コンテ・演出を手がけるこの三橋の中学生時代の回想シーンは、実は原作にはない、アニメ版『おおきく振りかぶって』にとって象徴的なシーンである。原作自体(複数の受賞理由に現れているように)、繊細な描写とともに競技としての野球を厳密に追求していることが高く評価されているところ、水島監督もまた、その緻密な競技性をアニメにする段において、その後の作品を予感させる方法論を本作にいかんなく導入している。その一つは、画面を緻密に配置することによって現れる重なり合ったリズム(polyrhythm)と偶然性(indeterminacy)のモチーフである(※1 例えば、アバンを経たBパートにおいては、三橋が西浦高校で会話ができること、声がけができることへと至る、リズムの調和(同期・回復)へと至る流れが明示されている。棒球(厳密にはナチュラルスライダーの亜種)と変化球を織り交ぜたテンポの良い投球の組み立てとその乗り越え。本作が最終的に至るのは、リズムの同期/ズレではなく、リズムの重なり合いである。第一話にはこの運動に参加する者たちの折り重ねられた視線交錯が既に予告されている。)。
本稿ではこの点を、同じく水島監督が脚本の筆をとった第1期第23話から、
①「ゲンミツに」(※2 第23話サブタイトル)、
②「5割(の意味)」(※3 西浦高校・栄口のセリフ「今日はこれで4打席バント。1回失敗してっからここで上げたら成功率5割だ。5割じゃ、バントの意味ねぇ!怖がんな!」)、
③「奇跡(の不在)」(※4 桐青高校のピッチャー・高瀬のセリフ「見ているほうはミラクルだなんだってはやすけど、あんなのやられてるほうが崩れているだけだ」)
という3つの語を借りつつ、3節に分けて掘り下げていく。
(2)「新設チームの快挙」といった物語(spectacle)ではなく
(以下略)
つかみの箇所だけで字数を食ってしまいましたので、そのあとの展開は本誌にて。
内容は下記の目次の通りです。
3、目次紹介
0. 0'00"00 よき観客(spectator)とは何か?
(1)運動の芸術(Art of Movement)
(2)「新設チームの快挙」といった物語(spectacle)ではなく
(a)第1期 第1−12話
(b)第1期 第13−25話
(c)第2期 夏大美丞戦
(3)運動の批評(Critique of Movement)
1. score 野球アニメにおける「ゲンミツさ」とは何か?
(1)起こりそうなリアリティから「ゲンミツな」運動のリアルへ
(2)意味のあるデータ/意味の無いデータ
2. play 「5割」のブレ
(1)からだを他人のからだのように
(2)即興に抗する身体
3. time 「奇跡(ミラクル)」の価値は?
(1)重なりあう音と声
(2)偶然性を設計する
4. 0'00"00 No.2 批評もまた始まる
以上
C90『アニメクリティーク vol.4.5 ガルパン特集号』記事紹介 Column 03. 注解(コンメンタール)戦車戦規則 #c90
(4.5目次など詳細情報は下記リンクにて)
上記アニクリ新号では、本編評論に加え、レビューコメント、コラムの充実を図っております。
テーマコラムは結果として11となりました。
以下は、1章にある3番目コラム「注解(コンメンタール)戦車戦規則」です。ご笑覧ください。
Column 03. 注解(コンメンタール)戦車戦規則
劇場版における大学選抜戦の戦車戦規則を検討する。主として検討するのは「戦車同公式試合規則〈高校生大会の規則〉」(以下「高規」とする。)、「廃校撤回念書」(以下「念書」とする。)である。
1、競技準備に関する規則
1-1 戦車登録
(1)使用可能車輌
使用可能車輌については、 「1945年8月15日までに設計が完了し、試作に着手していた車輌と、同時期にそれらに搭載される予定だった部材のみを使用した車輌」に限定される[高規3-01]。この制限以外には車輌種類に関する制限はなく、認可済車輌であればおよそ全て使用可能である。ただし、装備規定、とりわけ競技者保護のための安全対策(いわゆる「特殊カーボン」)規定により、オープントップの戦車は原則として使用できない[高規3-02]。大学選抜戦におけるカール自走臼砲は、通常使用であれば15人程度の人員が砲塔後部において装填を実施しなければならないものの、自動装填装置を装備していたことから、操縦手以外には屋外活動を展開するものは存在しなかったものと推察される。ここから、規定の趣旨に基づき「(オープントップでも)考え方次第でしょう」とする文科省学園艦局長の発言に繋がったものと理解しうる。
(2)車輌事前告知
以上に加え、時間的な制約としては、参加車輌については原則として48時間以内に連盟に提出された後、相手チームに告知される[高規2-01]。告知の趣旨を実効的にするため、48時間内における認可車輌以外は使用不可能である[同上]。この点につき、大学選抜戦においては、「試合直前の認可」という言葉が用いられているが、おそらくは念書を交わした後、試合開始までには少なくとも2日以上7日以内[念書第3条]のタイムラグが存在したものと思われる。
ただし、後述するように大学選抜戦においては重戦車T28やカール自走臼砲の存在は各々の会敵時に判明したことからわかるように、念書第4条に基づき、主催者権限により、競技者、参加車輌を記したメンバー表は交付されていなかったものと考えられる[高規2-01, 念書第4条]。
翻ってこの点が大洗女子学園にとっても奏功し、直前のメンバー追加を可能としたことは見て取りやすいところである。また、戦車種類についても「参加チーム」のものであれば足り[高規2-01]、必ずしも学園所有の車輌であることは要件とされていない。よって、クッション、ミルクセーキの材料、紅茶セットなどの持ち込みと同様に、戦車自体も「私物」として直前登録が可能である。
(3)車輌数制限
他、明文の規定が存在するのは車輌数制限[高規2-02]だけであるが、連盟の指定に基づくものであり、上限は定められていない。大学選抜戦においては、念書第4条により「30輌」であることは事前に主催者より通知されていた。このことから、大洗女子学園チームの30輌を超えた知波単学園の16輌は待機することとなった。
1-2 参加者登録
参加者は「参加チーム」に属するものであれば足りる。事実上は学園艦ごとにチームが分別されているため、原則として同校の生徒は別の「参加チーム」には配属されず[『アリス・ウォー』を参照]、反対に他校の生徒は同じ「参加チーム」にはなれない。ただし、廃艦命令後の人員移動指示にあるとおり、学園艦相互の人員移動も生徒会決裁により柔軟に行われることから、黒森峰ほか各高校の短期入学手続が可能となった。
その他、参加者に関する要件は戦車と同様に原則として48時間前の事前告知が求められるものの、大学選抜戦においては、念書第4条により事前告知は不要とされていたため、「参加チーム」の増員が認められた。
その他、年齢要件・身体要件などについても明文の規定は存在せず、免許取得及び安全管理[高規3-02]がなされうる以上は島田愛里寿のような若年者でも参加可能である。
1-3 実施要項
(1)殲滅戦、フラッグ戦
殲滅戦は「相手方の車輌全て」「競技続行不能」[高規1-02]、すなわち「競技資格喪失」[高規4-02]にすることによって、勝敗を決する試合形式である[高規1-01]。「競技資格喪失」は、判定装置(いわゆる白旗)[高規3-02]に加えて、審判員により続行不能と判断されることで成立する。修理補給が可能である限り、車輌故障は続行可能である。[高規4-03]
(2)時間・場所等に関する決定権者
主催者が決する。高校生大会については原則として連盟[高規2-01]が決するものの、個別の事案に応じる。
(3)補償
競技区域内で発生した建造物、路面などの原状回復については連盟が補償する[高規6]。エキシビジョンにおいては、大洗町役場をはじめとして、割烹旅館 肴屋本店及び大洗シーサイドホテル並びにアクアワールド茨城県大洗水族館が次々と破壊されたが、これらはいずれも高校生大会のため全て補償の対象となる。
これに対して、大学選抜戦については文科省預かりの事案ゆえに、参加者は使用許可地の維持に関して善管注意義務を負い、義務違反によって賠償責任を課されていた[念書第6条、第17条]。ただし、この点については違憲の疑いがある。
2、競技開始時、競技開始後の規則
2-1 開始号令、再開号令
競技者は、審判員の開始号令とともに競技場に侵入し、中止号令によって、双方の根拠地に後退する[高規4-01]。大学選抜戦冒頭、「待ったー!」の掛け声で黒森峰が乱入した時、すでに開始号令は発されていたが、事実上の試合開始は再開号令時であるため、開始号令後再開号令前の段階においてもメンバー追加が可能となった。
なお、メンバー追加に関する異議申し立てについては後述する。
2-2 アピール権、異議申立て
競技資格喪失条件[高規4-04]に該当する車輌については、車長は審判に対して、競技資格喪失の撤回をアピールすることができる[高規4-05]。このアピール権は、列挙事項である競技資格喪失に該当する場合でなければ行使できない。しかし、①アピール権の趣旨が資格喪失者の保護と相手方の利益の均衡を図る趣旨にあること(5分以内ルール)、②競技資格喪失条件[高規4-04]には専ら競技続行不能事由のみが列挙され、禁止行為による失格条件[高規5]には危険行為・不品位行為が列挙されていることに鑑みれば、競技資格喪失条件に準ずる場合であれば相手方の了承を得ることによって、利益の均衡を図ることは可能である。また文面上も、明確な「規則違反」が認定されていない場面[高規4-04]において、相手方に申し立ての機会を与え、アピール権行使の前段階としての調整を行うことには一定の合理性が認められる。
大学選抜戦において、審判である蝶野が「異議を唱えられるのは相手チームだけです」と述べた趣旨はここにある。
2-3 禁止行為
禁止行為[高規5]には、危険行為として指定された以外の用具・部材の使用、競技区域からの離脱、人間への発砲、競技続行不能車両への発砲があげられる。不品位行為としては、審判員・競技者への非礼な言動、無気力試合がある。いずれの行為を行ったものも、試合続行不能ではなく失格となる。
本件では、モーター規定の不整備をついて改造車輌が用いられていたが、連盟が事前に認めたものではない以上、おそらくは参加車輌規定における部材組み合わせ[高規3-01]で対応したものと考えられる。ただし、規定上は本来は参加車輌規定但書[高規3-01]に基づき連盟の認可を求めるべきであった事案であり、禁止行為と解釈する余地も十分にある。
以上
C90『アニメクリティーク vol.4.5 ガルパン特集号』記事紹介 Column 07. ボコられの系譜 #c90
(4.5目次など詳細情報は下記リンクにて)
上記アニクリ新号では、本編評論に加え、レビューコメント、コラムの充実を図っております。
テーマコラムは結果として10となりました。
以下は、2章にある7番目コラム「ボコられの系譜」です。ご笑覧ください。
Coliumn6.ボコられの系譜
(1)ボコミュージアムの応援 必衰必敗に抗して
おそらく係員の他には人っ子一人いないボコミュージアムの玄関には、ひとつのオブジェがある。何もしていないにもかかわらずボコボコにされる「ボコられグマのボコ」である。その「ボコ」を象ったロボット、通称・生ボコはミュージアムの顔であり、それゆえ正面玄関に鎮座しているわけだが、予算不足のためかひどく原始的な仕組みしか内蔵しておらず、同じ言葉をただ繰り返すだけのチープ感満載の機械仕掛けでしかない。ギシギシと鳴る軋み音とともに繰り返されるのは、「おう!よく来やがったな、お前たち。おいらが相手してやろう!ボッコボコにしてやるぜっ!」、「おっ、なにをする!やめろー!」、「やられたー! 覚えてろよ(ガクッ)」という通り一遍の挙動である。ここでツッコミ役・武部沙織が、「何もしてないって」と最早ツッコミの体をなさない機械的なテンドンに徹しざるをえないのは、ボコの単調さゆえである。
勿論、この「何もしていない」には二つの意味がある。①一つには物理的な攻撃を何一つ受けていないという意味であり、②いま一つには殴られる理由が何一つ無いということである。①物理的な刺激なしに自動運動を繰り返すボコは、通常人にとってはコミュニケーション不可能な対象(ツッコミ潰し)として現れるし、②殴られる理由が無いことは見るべき筋を見失わせ、「ナニコレ...」と嘆息せざるをえない単調な筋に結びつかせる。そもそもミュージアム自体が浦安の某施設のパクリであることからしても、資本・商業・娯楽的には見るべきドラマの起こらない場として朽ちていく宿命にあることは、想像に難くない。
しかし、このような常識に対して西住みほ(及び島田愛里寿)は、自動運動と単調な筋を体現する必衰必敗のボコを見て、目を爛々と輝かせていた。勿論その答えは(もはやボコのアイデンティティと化した)必衰必敗の「結果」を、みほと愛里寿が望んでいることにはない。みほの「退いたら道はなくなります」や、愛里寿の「私が勝ったらボコミュージアムのスポンサーになって欲しいんだけど。このままでは多分廃館になっちゃうの」というセリフを思い出そう。彼女らは結果の必然ではなく、ボコショーにもあったように「次」という言葉を携え、必然に抵抗するボコのあり方に感化されていた。
ボコはいつも負け続ける単調な筋の中にあって「次は頑張るぞ」と述べる、言行不一致の矛盾を抱えた存在だ。だからこそ、西住流と島田流、盛者必勝の二つの道の後継者だった彼女たちは、自身に宿命的に課された必然に抗う道を模索しているのではないか? 既定路線とはずれた「すごく頑張ってた」ボコの姿を見い出すことで、「次」に感化される立場を、ここで保持したがっているとは言えないか?
「何もしていない」ところに何かを見出すこと。一つの筋しかないところに分岐する「道」を見出すこと。必然の中に「次」に向けた態度を形成すること。オブジェの中に主客の転倒を見出し、「ボコリボコられ生きていく」術を学ぶ、彼女らなりの戦車道の萌芽が、ここに見て取れる。
(2)遊園地戦のチームワーク 抵抗する二つの戦車道
とは言え、彼女たちの動機は全く同じ訳ではない。
片や愛里寿にとってボコは、必然としての資金不足や力不足ゆえに耐えず傷つきうるがゆえに、「私が助けてあげるからね」と言葉を掛けるべき、か弱い主体として現れる。片や、みほにとってボコは、「困難な道」でも「厳しい戦い」を回避することが決してない(ただし貧弱な)主体として現れる。愛里寿にとってのボコは脆弱な他者であり、みほにとってのボコは非力な我々のうちの一人として現れる。愛里寿がボコを籠の中に囲うのに対し、みほはボコを自らの部屋に住まわせているのは、この分岐の表れだろう。
西住流ならぬ西住みほの戦車道のモチーフがここには現れている。奇策を用いない正道でありながら「型どおり」でもない、車両数や戦力に基づく分析を覆しうるチームワークを生かした戦法がそれである。TV版最終話で一対一のフラッグ車同士の戦いに持ち込んだ分断作戦のみならず、劇場版後半における大洗女子学園チームの攻防は、分散的意思決定に基づき急造チームにおける役割分担を随時進めていく方式を採用していくことになる。伝統である突撃を封印し、特殊迷彩を活かした(?)ゲリラ戦を展開した知波単学園を筆頭に、基本的には平面的なゲームである戦車戦を(GPS役を担うことで)立体的なゲームに変えるアンツィオ高校、「重戦車キラー」を返上して「軽戦車キラー」へと転身した一年生チーム、「優雅な勝ち方」を返上して「データ主義」に徹した聖グロリアーナなど、各車は自車の最善ではなく、一つの戦場における配置の最善を期して、大洗の勝利のために邁進するに至るのだ。
(3)最終戦のヴォイテク 視聴者はスキをあきらめない
もし深読みを続けるなら、ここで最終戦の戦いを一時中断させたボコ風の乗り物(ヴォイテク)のことを思い出すことができるかもしれない。
センチュリオンと4号戦車の間にヴォイテクが歩みを進めたのは、単なる偶然の所産である。しかし、この偶然は(決して外部の刺激に反応することがなかった)ミュージアムの生ボコとは異なり、彼女らの戦いの中で生じた瓦礫への衝突によるものである。つまり、彼女らがボコとコミュニケーションを取りたがっていたその希求は、この場面において意図せざる形で成立しているのである。
センチュリオンと4号戦車の間にヴォイテクが割り込んだことは、当然ながら「出来すぎ」の筋書きのように思われるかもしれない。しかし、ここで彼女らは、ボコのことが「スキ」である(だから撃てない)ということとともに、ボコが「割り込んだ」(だから撃ってはならない)ということを重視しているように見える。少なくともみほと愛里寿の間では、「ボコ」が彼女たちの二つの戦車道の間で生じた試合を司っていることが、ここで示されている。
だからこそ、自らの負けを導いたヴォイテクに乗った愛里寿が、かつてみほから譲ってもらったボコのぬいぐるみを「私からの勲章よ」と差し出すことは象徴的だ。もちろん彼女たちはいずれかの勝利のために戦っていたのだが、勝利はボコを失うことやボコに負けの原因を帰することで成立するわけではない。ボコは勝者と敗者のいずれかにも帰属することではなく、互いに交換される「わだかまりのない」戦闘の証であり続けることに、その意義があるのだろう。そこでは、どちらかに勝者と敗者が振り分けられることが必然であるという理由で、試合が無意味化するわけではない(両勝ちというものがありうる)ということが、ご都合主義とは別の形で示されているのである。
・・・
さて、ここから先は錯覚体験の記述である。
必然であるという理由で抵抗を諦めない(スキを諦めない)のは、みほだけではない。劇場を見て応援していたみほのように、画面を見つめる私達もまた、一つしかない筋を見に、何度となく劇場へと足を運んだだろう。ボコミュージアムの正面にある生ボコの同じ動きに目を釘付けにされていたみほのように、視聴者もまた、同じ画面に釘付けにされ、また釘付けにされたいと望んでいたはずだ。
ヴォイテクが彼女たちを制止するかのごとき歩みを進めた時、一視聴者である私は、目を画面に釘付けにされながら、みほと愛里寿の不毛な戦闘を止めたいという欲望と、この素晴らしい戦闘をいつまでも続けて欲しいという願いを、ヴォイテクが一瞬だけ叶えてくれたように錯覚した。
もちろん、この錯覚は一瞬でしかありえない。しかし、もしボコがみほにとって並列的に存在するように、我々にとってのキャラクターへの錯覚がありうるとすれば、このようなボコを介した試合への(錯覚的な)介入という方法でしかありえなかったのではないかとも思うのである。ボコがキャラクターを見る刹那において、私たちはキャラクターの目線を感じられた。そのような錯覚こそが、視聴者が何度も同じ試合を見に足を運んだ理由だとするならば、それは幸せな錯覚と呼んで差し支えないように今なお思えなくもない。私は抵抗=スキを諦めない。
以上
C90『アニメクリティーク vol.4.5 ガルパン特集号』記事紹介 (1−2_01) Column 03. 爆音轟く無声映画---付:「極上爆音上映」トーク総括 #c90
(4.5目次など詳細情報は下記リンクにて)
上記アニクリ新号では、本編評論に加え、レビューコメント、コラムの充実を図っております。
短く読めるテーマコラムは現状6つですが、まだまだ増える可能性があります。
以下のような体裁で各種各様のテーマを検討しておりますので、ぜひ「こんなものも検討してほしい!」とか「自分で評論は書かないけどここは気になった!」とかご意見ございましたら、ぜひお寄せください。
以下、コラムの3つ目、「Column 03. 爆音轟く無声映画---付:「極上爆音上映」トーク総括」となります。
Column 03. 爆音轟く無声映画--- 付:「極上爆音上映」トーク総括
(1)マクロの視覚、ミクロの聴覚:刹那における信と知
敵戦車の砲塔が十字を切ったら注意し、砲塔が止まったならば死を覚悟しなくてはならない。照準を合わせる段階において横移動は方位、縦移動は距離(高度差)の割出しを意味している。
光は音よりも早く到達するので、ここで耳を澄ませていては回避にはおよそ間に合わない。縦移動が完了したことを目視した刹那のうちに、相手の砲弾は我々を貫くに至るだろう。
一方で、耳は、識別能力から言えば目よりも精密な器官である。目が50分の1秒ほどの明滅(ルビ:フリッカー)しか認識できないのに対して、耳は1000分の1秒のズレを認識することができる。
だから、視聴する側から見れば、画面の表面の精緻さと運動の厳密さに加えて、我々はより信頼のおける音をリアルな世界把握の源泉にしているものと思われる。
マクロでは視覚がより信頼に値し、ミクロでは聴覚がより信頼に値する。この客観的な物理と主観的な識別のズレが『劇場版』では強調されていた。
例えば最終戦において、会話は咽頭マイクを通じてなされているものの、視聴者にその声は届かない。エキシビジョンを見ている観客たちに聴こえているのと同様に、最終戦にあるのは、戦車の発する砲撃音、エンジン音、旋回に伴う軋み音の他には遊園地遊具が次々と破壊されていく音だけだ。
戦闘における指令(「こうすればああなる」)はここで頓挫し、ただ未見・未聴の刹那にある世界の事実(リアル)だけが残される。
(2)極上爆音上映と遅延の功罪
さて、自らも音響監督を兼務することもある水島監督作品は、監督オーディオコメンタリーやインタビューでもしきりに「音」へ言及している通り(参照:『ガルパンの秘密』監督インタビューなど)、以上のような音と映像の関係についての並々ならぬ拘りを見せる。
本作でも音響へのこだわりは随所に見られ、その表れとして立川「極上爆音上映」を筆頭とした各所の音響上映の成功につながっていると見ることができる。
そこで、立川における音響チームの3名とプロデューサーによるトークショー(2015.12.26)を振り返りつつ、以下紹介しておこう。
トークショーは、まずは立川シネマシティの音響へのこだわりを示す、剥き出しスピーカー等の音響設備の特殊性、レコーディングスタジオのような壁面床面構造・音響調整卓の存在に触れるところから始まった。その後、各場面における音へのこだわりポイントを(センター/LR/後方スピーカー、サブウーファーごとに音を分解しつつ)解説していく流れで進行していった。
実演で取り上げられたシーンは3つである。
(1)冒頭の茶柱シーンの会話では戦車チャーチル内の反響音を意識した音作りへのこだわり、(2)「戻りなさい、ローズヒップ」のシーンでは、無線を介した会話における効果の調整へのこだわり、(3)継続高校戦闘シーンでは、セリフ、音楽「Säkkijärven polkka」、効果音の組み合わせへのこだわりが、それぞれ確認されていった。
興味深いコメントとして、録音調整の山口氏から「仮に音が識別できないとしても、そこにあるわずかな違いを感じてほしい。そこにこそリアルがある」という旨のコメントがあったことである。
識別されないなら差異はないのではないかと突っ込みを入れることもできるだろうが、この趣旨はおそらく、最初は聴き分けられないだろう微妙な差異を、再視聴や低速視聴、コマ送りなどを介して、そこにあるリアルを掴み取って欲しいというメッセージであるのだろう。
最後に、多人数制作で仕上げの時間がとりづらくなってしまうハリウッドシステムとの違いとして、音響効果を一人に絞る『ガルパン』の仕組みが今回は奏功したのではないか、という言及で、トークショーは閉じられていた。
・・・
筆者としては非常に満足して家路に着いたわけだが、一点だけ、トークショーにおいても言及されなかったシーンでどうしても気になってしまう箇所が残った点に触れておきたい。それは、エンドロールで流れる「piece of youth」の重低音である。
本編の重低音に力点を置いた調整の結果であろうか、この劇伴の重低音箇所が筆者にはどうしても1/4拍ほど遅れて聴こえていた。
誤解がないように言っておけば、周波数帯における伝達速度の差異は存在しないため、低音が遅れて聴こえるというのは事実に関する話ではなく、あくまでも視聴者の認識に関する話である。
つまり、物理的には重低音だろうが高音だろうが速度に違いはないのであるが、重低音は音の立ち上がりからのサスティンを認識するまでに時間がかかる。そのため、アタックが認識されにくく、皮膚や服が振動された後になって「ドンッ!」と低音が響くように感じたのだろう。
しかし、この遅延の経験もまた、エンドロールの幸運ともいうべきか、視聴の快楽の資源となる。大洗女子学園への短期入学という刹那の邂逅を終えて帰省する各校メンバーを、遠ざかりつつ見送るかのような錯覚に、視聴者を駆り立てるのである。
この遅延は、再視聴や低速視聴といった作品への接近のみならず、視聴者の意識していなかった未聴の新たなリズム(への信頼)を浮きだたせてくれるのである。
(3)轟音の最中にある無声映画:「刹那主義には賛同できない、でも、彼女たちを信じよう」
認識に上らない音、聴こえない音は(少なくとも主観的には)存在しないのと同じだ。しかし、本作において聴きとれない音、あるいは遅れて聴かれる音は、私たちに聴こえない音を(想像するのとは別の仕方で)聴かせてくれる。
その未聴の音は、轟音にかき消された無声と遅延前の刹那にある二重の「アタック(頭音・急襲)」に追いつくように、視聴者を鼓舞するだろう。
この点を確認すべく、いま一度、対カール自走臼砲作戦に戻ろう。
そこで継続高校・ミカは、急襲によって周りを守る戦車の引き付けるよう指示を受けていた。一見無謀とも見える作戦に対し、ミカは「刹那主義には賛同できない」と言葉を向けるが、その刹那の「彼女たちを信じよう」と言ってカンテレを(はっきりとしたアタック音とともに)爪弾き始め、「Säkkijärven polkka」の律動を響かせる。
この場面こそ、音の間を縫う連携が最も冴えわたるシーンである。
リズムに乗ったBT-42は相手戦車の目を引きつけ、まんまとリズムに乗せるに至る。肩を弾ませリズムを埋め込むミカ・アキ・ミッコは、互いの動きを同期させつつ相手のリズムを撹乱する。履帯を外したクリスティー式BT-42、その最高時速75kmの俊足は、敵戦車を追い越し、彼女たちの軌道の狭間に引き入れる。そうして最後、ミカの「Tulta」の声の後、遅延された刹那の間を以ってアキは敵戦車を砲撃・撃破するに至るのだ。
かくして、『劇場版』においては、爆音が轟き渡る戦場における聴かれるべき音が、潜在的な形で聴かれうる。音はモノとして確かにここにある、視聴者はそう信じることができるはずだ。しかし、音のみならず、画面を取り巻くすべてのモノの中にサインが散りばめられていることをも、今や私たちは信じられるだろう。
この信ゆえにこそ、本作は極上のサイレント映画と呼ぶに相応しい。轟音で何も聴こえない中、その反対にすべての潜在的な音が立ち上がる刹那に、本作を前にした視聴者は直面するのだから。
以上
アニメクリティークvol. 5.0「アニメ化する資本・文化・技術/不条理×ギャグアニメ特集」発刊

目次
Nag 巻頭言
第一部 Technology and social capital.
Nag 導入文
おはぎ ロボットアニメにおける手描きとCG
tacker10 積層する断片(コマ)、拡張する断片(コマ)、思考する断片(コマ)ーーアニメ『灰と幻想のグリムガル』論
makito×Nag 視線をはじくものーー『戦場でワルツを』及び『コングレス未来学会議』
橡の花 「撮られるべきもの」たちについてのノート
ケンイチ 『フリップフラッパーズ』の鑑賞法ーー燦めく個々のSerendipity
Nag 第一部取りまとめーー『苺ましまろ』と「なんとなし」の時間
第二部 Absurdity and Gag.
すぱんくtheはにー アニメーションに救われてーー“不”条理ギャグ、“未”条理の自己組織化、条理というエラー
ケンイチ 不条理という土壌に顕れるもの
Dieske 『ガールズ&パンツァー』評ーーなぜ少女たちの身体は傷つかないのか
Nag 第二部取りまとめ この「無駄遣い」アニメたち_『このすば』×『フリフラ』×『おそ松さん』
第三部 Art-i-fact and Cultural Capital.
ウインド 落語アニメであり、反落語アニメでありーーアニメ『じょしらく』論
SdRk 「お客」の哲学ーー『昭和元禄落語心中』論
あんすこむたん 落語心中ーー伝承と死神
今村広樹a.k.ayono ギャグアニメとしてのじょしらくについての断章
あんすこむたん キズナイーバー 心と体をつなぐ痛みーー痛みを繋げるとはどういうことか
Nag 第三部取りまとめーー「客」の階層間社会移動のための枠保障
Cap.
奥付

1、検討・寄稿募集作品例:
(概ね2010年以降における)アニメ制作の特徴・環境・変化を読み取ることのできる任意のアニメ作品。
※ 2010年という区切りは便宜的なものです。編者の念頭には、深夜アニメ放映数の急激な増加や3DCGの全面的なアニメへの導入、ショートアニメのTV放送枠の拡大などなどの画期的変化がありましたので、時代区分としてひとまず設定しました。他の観点から、より遡るべき適切な区分が存在する場合には、その旨を明記しつつ作品を自由に選定くだされば幸いです。
対象作品例:
(見通しをつける趣旨での例示であり、作品を限定する趣旨ではありません。複数カテゴリーにまたがるものは順不同で記載)
(1)第一部「アニメ化する資本・文化・技術(art)」
①VR、アニメ化する身体
「コングレス未来学会議」「戦場でワルツを」
「屍者の帝国」「ハーモニー」
「てーきゅう」「無彩限のファントム・ワールド」
「ガラスの花と壊す世界」etc
②資本/文化/芸
「昭和元禄落語心中」
「すべてがFになる THE PERFECT INSIDER」
「スペース☆ダンディ 」「キルラキル」
「四月は君の嘘」
「C」「狼と香辛料」「ワールドエンドエコノミカ」
「じょしらく」etc
③技術:美術、撮影、CG(※挙げればキリがないのでごく一部のみ)
「甲鉄城のカバネリ」
「灰と幻想のグリムガル」「亜人」「GOD EATER」
「機動戦士ガンダム サンダーボルト」
「響け!ユーフォニアム」「境界の彼方」
「楽園追放 -Expelled from Paradise-」
「バケモノの子」
「シドニアの騎士」「蒼き鋼のアルペジオ」「RWBY」
「蟲師」etc
④制作プロセスの可視化
「少女たちは荒野を目指す」
「SHIROBAKO」
「アニメーション制作進行くろみちゃん」
「妄想代理人」etc
(2)第二部「作画×ギャグ×不条理」
①作画(※挙げればキリがないのでごく一部のみ)
「プリンス・オブ・ストライド オルタナティブ」
「リトルウィッチアカデミア」「同級生」
「ガンダム・ユニコーン」
「ワンパンマン」「血界戦線」「ローリング☆ガールズ」
「かぐや姫の物語」
「終わりのセラフ」「アカメが斬る!」
「Fate/Stay Night UBW」etc
②不条理ギャグ
「おそ松さん」
「だがしかし」「監獄学園」
「月刊少女 野崎くん」
「侵略! イカ娘」「のうりん」
「日常」「みなみけ」
「さよなら絶望先生」
「百合星人ナオコサン 」
「苺ましまろ」etc
③異世界転生ほか
「この素晴らしい世界に祝福を!」
「Re:ゼロから始める異世界生活」
「ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った?」
「ノーゲーム・ノーライフ」
「はたらく魔王さま!」
「ソードアートオンライン」
「ゼロの使い魔」etc
※ なお、劇場版を含む〈物語〉シリーズについては『vol.6.0』取扱予定となりますので省いています。また、『アニメクリティーク』誌の前号までで取り扱った諸作品についても幾つかは意図的に省かせていただきましたが、再度取扱うことも前向きに検討しています。ご意見お寄せください。
※ 上記のリストで概ねどこに着目して選定していいるかは浮かび上がってくると思いますが、他により適切な作品がありましたら是非編集(@nag_nay)までお寄せください。リストの充実に資するために、検討・採用させていただければ幸いです。
2、寄稿募集要項
(1)募集原稿:
アニメ作品のうち、寄稿募集原稿例に掲げた作品(など)を中心として、「資本・文化・技術」あるいは「作画・ギャグ・不条理」に絡めて論じられるもの。二つの特集を接続するものも推奨です。
(2)装丁・発刊時期:
オフセット印刷、A5、100頁程度で企画しています。
発刊時期は、2017年春の第24回東京文フリ(5月)を想定しています。
(3)募集原稿様式
a. 文字数:
①論評・批評 : 3000字程度から15000字程度まで。
②作品紹介・コラム:500字程度から2000字程度まで。
b. 形式
.txt または .doc
c. 締め切り
第一稿:2017/2/1 (※注:内容充実のため延長しました)
(※ 個別に連絡いただけましたら延長することは可能です)
(※ その後、何度か3月中旬まで原稿の校正上のやり取りをさせていただけましたら幸いです。)
最終稿:2017/3/31 (※注:内容充実のため延長しました)
d. 送り先
anime_critique@yahoo.co.jp
※ 参加可能性がありましたら、あらかじめご連絡いただけましたら幸いです。その際、書きたい作品、テーマ、内容についてお知らせくださると、なお助かります。
※ 原稿内容について、編集とのやりとりが発生することにつき、ご了承ください。
(4)進呈
寄稿いただいた方には、新刊本誌を進呈(※ 進呈冊数は2を予定)させていただきます。
3、企画趣旨: アニメ化するのは誰か? アニメ化していくのは誰か?
第1、特集1:アニメ化するための/自らがアニメ化する資本・文化・技術
(1)資本・文化・技術(art)の分節化
次号特集1「アニメ化する資本・文化・技術」には、少なくとも2つの意味合いが含まれている。[1] 一つには、アニメを作り上げるための(=アニメ化するための)基底となる資本・文化・技術(art)という意味合いであり、[2] いま一つには、アニメを作り上げる資本・文化・技術自体が戯画的・アニメ的(caricature)な形でアニメを参照し、再帰的に自らを構成しているという意味合いである。
[1] まずは第一の点について。
現在、アニメは視聴者にほど近いコンテンツとして、地理的、世代的、娯楽的な制約を超え出る広大な裾野を持っているかに見える。(折しも新たに企画されたと伝え聞いた)日本博(ジャポニスム2018)の開催など、コンテンツとしてのアニメ「利用」は拡大の一途を辿っている。
しかし、アニメが視聴者にとって第一義的にはコンテンツ(趣味判断の対象)として現れるとしても、云うまでもなくアニメ制作それ自体は第一義的にはコンテンツではない。
アニメが視聴者に届くまでの間には例外なく、①アニメを受容する層との関わりで放送枠(本数)が決定される自生的な環境形成のプロセス、②制作会社・放送局・出版社・スポンサーなどが長い時間と多大なコスト、各々異なる商業的意図をかけて行う企画のプロセス、③資金リスクや権利問題を縮減するための経済-法技術的プロセス、④そして何より脚本・絵コンテ・レイアウトから原画・動画・美術・撮影etcに至る制作のプロセスなどなどの諸プロセスが控え、潜在している。
とりわけ最後の④制作プロセスについては補足が必要である。そこでは、(4-a.)技術的な側面のみならず、(4-b.)労働環境や教育訓練の側面における問題をも含んでいること(またこれに対抗する形で、『亜人』劇場版とTVシリーズを同時並行で進めることに成功したポリゴン・ピクチュアズの記事などにあるように、プリプロを詰めることによって問題解消の動きが広まっているとのこと:「亜人」から広がるポリゴン・ピクチュアズの今後 ― 瀬下寛之総監督、守屋秀樹Pに訊く(後編)http://www.inside-games.jp/article/2015/11/30/93537.html (前編)http://animeanime.jp/article/2015/11/29/25885.html)がよく知られるところとなっている。
また『アニメスタイル007』記事で明らかにされているように、(4-c.)2015年視聴者を震撼させ、劇場版も上映中の『響け!ユーフォニアム』では、美術・撮影段階が(単に役職名の追加にとどまらずに)既存のアニメ工程とは異なる形で非常に重視されていることが見て取れる。他にも近年の作品で言えば、背景美術への関心を感じさせる『灰と幻想のグリムガル』や、新たに"化粧"工程を加えた『甲鉄城のカバネリ』、あるいは劇場版アニメ『バケモノの子』や『蟲師』においてもこの点は顕著かもしれない。
(4-d.)勿論、このような既存の制作現場・制作工程自体の変化は美術に限らず、CG工程においても起こっており、日本でのフルCGの本格的な進化を示す『楽園追放』や『シドニアの騎士』『蒼き鋼のアルペジオ』(本邦の作品ではないが『RWBY』)など近年のアニメを技術・資本環境とともに分析するためには、避けて通れない視点となるだろう(詳しくはCGワールド記事などを参照)。
最後に、(4-e.)NPO法人アニメーター支援機構などの存在は、アニメを視聴する我々と制作サイドの距離の変動を示す一つの徴候と言えるかもしれない。
・・・
以上つらつら述べてきたものの、第一の点の主眼は、上述のようなトリヴィアルな事実を指摘することそのものにはない。「個的で純粋な趣味判断こそが全体的な資本・文化・技術に依存的である」という上述の指摘は非常に単純なものであり、理論それ自体としては合意を得られやすいものではあるだろう。しかし、その転倒を指摘することを超えてアニメをめぐる環境を実践的かつ批判的に考察する段になると、途端に大業な問いが立ち現れるためだ。
【TVの前あるいはPCの前でボタンを押すだけで映るコンテンツとしてのアニメの前には、上述のような企画制作へと至るプロセスがあり、当該プロセスの中には各々異なる利害を持った声が入り込むことで絶えず"綱引き"が生じていることが目に明らかだ】としても、その"綱引き"が常態化することを前提とした「政治的正しさ」や「商業的な無難さ」「権利保護を前提とした保守性や比較考量」などといった「正しい」奔流に抵抗することには、非常な困難が伴う。否、「正しさ」をめぐる闘争すらそこでは引き起こされることがなくただ流されてしまうこと自体が、アニメ評論の困難と言えるかもしれない。
このように、一見したところのアニメの地理的、世代的、娯楽的な広がりとともに、アニメの「正しい」自己抑制や陳腐化が同時に進行しているとするならば、まずは、その拡大と縮小のプロセスや先鋭化と保守化の鬩ぎ合いを表裏一体のものとして分析する必要がある。その分析は、最前線の橋頭堡に立つアニメ関係者へのささやかな援護を期したものでしかないが、アニメを作る環境(兵站)改善の役割をこちら側が法的・経済的・政治的に引き受ける基礎をなすものではありうることと考え、第一の趣旨を掲げた次第である。
そこでは(昭和落語との心中を語る『昭和元禄落語心中』ではないが)、文化や資本との応酬や協働関係をそもそものはじめから抱えつつ、取り込み、延命を果たしてきた大衆芸能の存立条件をも、この特集を機に詳らかにしていきたいと考えている。(世代を超えたバトンの渡し方があまりにも巧すぎた『スペース☆ダンディ』を雛形とするのは、あまりにも他の作品にとっては課題な要求かもしれないけれど、当該作品はその傑出した例である。)
・・・
いずれにせよ、視聴者が見ているアニメは、(視聴者主観から言えば)当世的な支持を受けた膨大なコンテンツの一つであるとともに、(環境側から言えば)様々なプロセスを通過する中で「厳正な」選別を受けた類稀なる制作物でもある。
【「作画崩壊」や「紙芝居」といった外野からの野暮な揶揄でも、反対に製作会社に過度に寄り添った諦念的受け入れや無条件の支援でもない形で、アニメ制作環境の多様性確保を達成する方法を考察することはできないか?】 この問いと共に、商業・流通・技術・文化といったコードの制限を掻い潜って作り上げられたアニメから遡って、制作へと至る資本・文化・技術(art)に関する諸条件を分節化する(articulation)とともに再構成することを、「アニメ化する資本・文化・技術」パートでは練り上げていきたいと考えている。
(2)資本の模倣芸術(Economimesis)の先鋭化
[2] 第二の点について。
さて同「アニメ化する資本・文化・技術」に関する第二の指摘は、上記のようなアニメ化を作るための諸基底とを前提としつつも「その諸基底自体がアニメという現象を再帰的に反復(構成)しているのではないか?」という仮説から出発している。
この仮説は、製作側の視聴者に対する「媚び」問題や原作モノを用いたメディアミックスの蛸足化、もはや通俗化したと言ってよいだろう意図的な聖地化(萌えおこし化)といった例に現れるような、視聴者の視線を先取りする(その共軛関係が『神々の歩法』さながらに阿吽の呼吸によるものなのか、ズレたリズムを含み持つものなのかはここでは問わない)製作と視聴者の共同作業に関わるものである。
あるいは、『少女たちは荒野をめざす』『SHIROBAKO』『ハケンアニメ!』(あるいは古くは『アニメーション制作進行くろみちゃん』『アニメがお仕事!』)のような視聴者の制作プロセスへの興味関心を背景とした自己言及・コンテンツ化にも、密接に関わるものである。
ここで『コングレス未来学会議』の「でもここから先はアニメーションしか入れません」というセリフを思い出しても良いかもしれない。同作の世界は、資本(Capital)と幸福の行き着く先にある、リアルに生きることとアニメの世界を生きることがほぼ等価になったディストピア的世界である。そこで主人公は、未来を変える大文字の(Capital)会議(Congress)への参加条件として、自分を生身の人間側ではなくアニメ的な意匠を纏うよう義務付けられる。アニメの意匠に自身を変じさせない限りは人間が人間のままで未来の門をくぐることは許されない(しかし勿論、外的な強制はされない)というこの場面は、アニメ化するための基底自体が資本・文化・技術環境に流されるがままに戯画化=アニメ化していくプロセスを同時に示している点で、本誌にとって非常に示唆的である。
ここでは、アニメ制作自体がアニメ的であろうとする戯画的な現象一般を問おうとしている。技術環境を背景として、(実際にはスケジュール上ほぼ不可能ではあるのだが)視聴者と制作との間のリアルタイムな応酬が辛うじて可能にみえるばかりに、視聴者の世界的な広がりや慣れといった条件にアニメ制作側(資本、文化、技術)が過度に拘束されているようにみえる点も、その一端として理解できるだろう。
・・・
繰り返しになるが、〈資本〉といった時には上記のアニメ製作資金のみではなく声優のアイドル化(アニメ雑誌へのインタビュー記事の多さはその一例であるだろう)やアニメーター育成といった人的資本、アニメに付随する政治的・経済的・社会関係的な文化資本、そして『コングレス未来学会議』が戯画的な形で示したような視聴者自身の物理的な身体反応そのもの(=快楽の活用)もまた、アニメというメディアの一部をも含むものとして把握できるだろう。
あるいは、〈文化〉といった時にも、大衆文化それ自体であるのみならず、大衆文化への再焦点化(『昭和元禄落語心中』や『じょしらく』)であったり、アニメ製作における社内文化、アニメ視聴自体の(良き/悪しき)教養化をも含みうる。最後に〈技術〉もまた、アニメ制作における作画、撮影、効果といった各テクネーを分節化しつつも、視聴者に現象するアニメの技法一般(art)をも含むものである。
この点では、既刊vol.3.0のタイトルにある人工物(artifact)の問いや、お約束を含む芸(art)、そして芸自体が時代を通じて新陳代謝し、持続するための条件についての問いをも射程に含んでいる。『フリクリ』のように、とは言わないが、視聴者の反応を先取りするのでも拒否するのでもなく極限まで先鋭化した作品を生み出すようなアニメの緊張関係を析出することが、第二の趣旨の課題である。
第2、特集2:作画、ギャグ、不条理
以上を踏まえて、第二部では「作画、ギャグ、不条理」という括りを用いて、幾つかのアニメ作品を横断的に論じていきたいと考えている。
ともすればアニメ評論誌においては、単に多岐にわたる物語を要約したり、そこに一つの筋をつけるだけに終わってしまう評論も多々見受けられる。このような評論に対する自己批判も兼ねて、本誌では筋からの逸脱と取り込みの運動を内部に組み込む「ギャグ」に焦点を当てることとした。加えて、ともすればアニメーター追跡自体が目的になっているかに見える作画についての分析を評論の文脈と接続する必要から、作画アニメと呼ばれるジャンルとギャグアニメ(特に不条理ギャグアニメ)を同時並行で論じてみてはどうかと考えた。
ここでは多くは論じられないが、『おそ松さん』の商業的成功をやはり無視することはできないし、近時の『このすば!』を筆頭として異世界転生というジャンルが長い時間をかけて形成され、現在に花開いている事態もまた軽視することはできないと考えている。
特集1の「アニメ化する資本・文化・技術」の深堀りを期して、幅広い作品を放り込める特集2の作品群を縦横に論じていただきたいと、編集側としては考えている。
以上